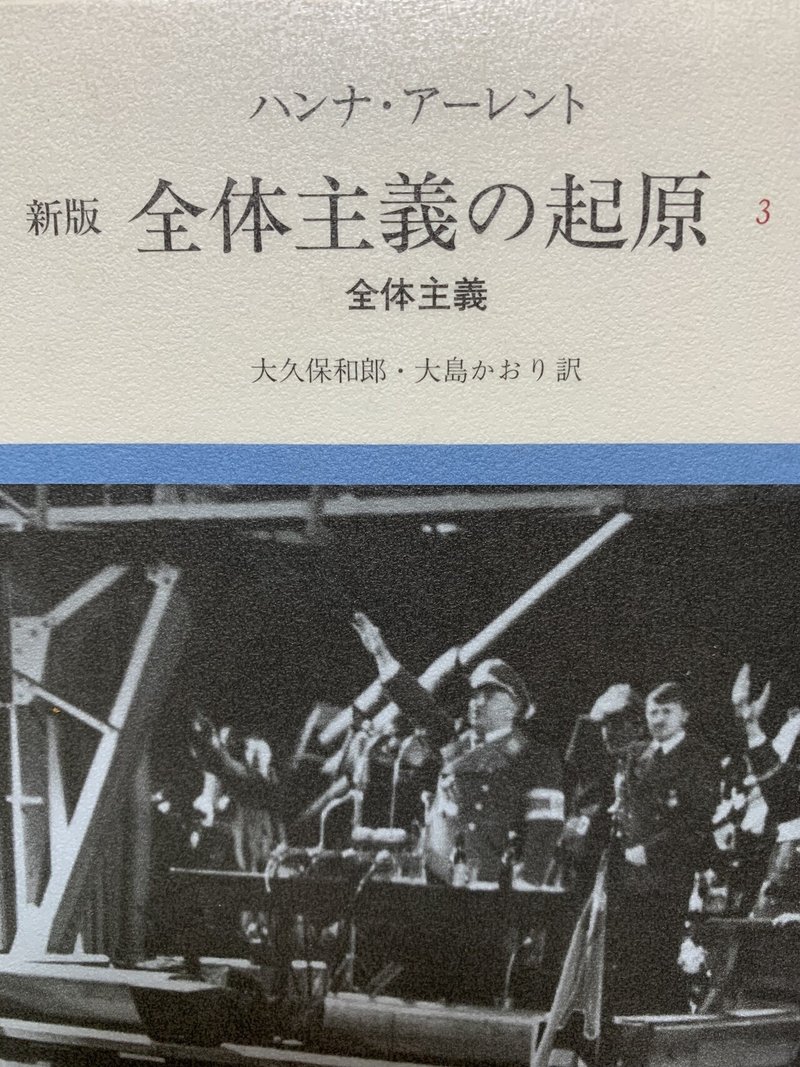本の花束(11)ハンナ・アーレント『全体主義の起源』(みすず書房、2017年)
『ハンナ・アーレント(2013)』が岩波ホールで公開され、インディペンデントシアターだけに珍しくヒットしました。わたしも公開時に劇場で観て、DVDをさっそく買って何度も観ました。
内容はハンナ・アーレントがエルサレムでのアイヒマン裁判をすべて傍聴し、雑誌『ニューヨーカー』に連載します。それらを『エルサレムのアイヒマン――悪の陳腐さについての報告(1969)』――映画では「悪の凡庸さ」と訳していますが――として出版しました。とにかく悪は一見かっこ良くて憧れるが実は浅はかなものである、悪は根源的ではない、根源的なのはむしろ善である、という主張でした。
SS中佐でホロコーストの中心人物であったアイヒマンは、「これまでユダヤ人を殺せという命令は出していない」「上からの命令に従っただけ」と言い逃れをします。ナチスは官僚的な組織だと感じたアーレントは、「ユダヤ人虐殺という世界的に残酷な歴史を刻んだ悪は、まったく何も考えていない」と書いて、「正義」の側としては「この冷酷なナチ女!」と猛烈に批判し、彼女は世間から反感を買いました。確かにアーレントはアイヒマンを庇っているように読めたのですが、決して感情的にならず、冷静客観的に裁判の様子を書いたのです。
彼女はドイツ系ユダヤ人として生まれ、ナチスが政権を獲得しユダヤ人迫害が起こるなか、一度は逮捕される危険もありましたが、1933年フランスに亡命し、1940年フランスがドイツに降伏して、ユダヤ難民援助のソーシャル・ワーカーなどとして働きながら(ユダヤ女性ラーエル・ファルンハーゲンの伝記を仕上げ、反ユダヤ主義の研究を進めた)、翌年アメリカに亡命しました。その後習得した英語で多くの著作を書き、ドイツ語圏の作家の著作の英語への翻訳・出版にも携わりましたが、彼女が思考する際の言語はドイツ語でした。余談ですが、マルガレーテ・フォン・トロッタ監督は「アーレントの哲学的に思考する姿は、バルバラ・スコヴァが一番である」とのことで、彼女が採用されました(バルバラ・スコヴァは『ローザ・ルクセンブルグ』の主演を務めています)。
『全体主義の起源』を1951年に英語で発表し、それを加筆・修正したドイツ語版を1955年に刊行しました。「第1巻 反ユダヤ主義」「第2巻 帝国主義」「第3巻 全体主義」があり、ドイツ語版序文をカール・ヤスパースが書いています。大学時代のアーレントはカール・ヤスパースの教え子でした。彼が序文で「3巻の最後を最初に読めば結論がわかるから、全体の流れをよく把握できる」と書いてあり、わたしもそれに従って読みました。タイトルは「イデオロギーとテロル」です。以下、非常に長いのですが、引用します。
孤立は人間生活の政治的領域に関係するにすぎないが、独りぼっちであること(ロンリネス)は全体としての人間生活に関係する。たしかに全体主義的統治はすべての暴政と同様、人間生活の公共的領域を破壊することなしには、つまり人びとを孤立させることによって彼らの政治的能力を破壊することなしには存在し得なかった。しかし全体主義的支配は、統治形式としては、この孤立だけでは満足せずに私生活をも破壊するという点で前例のないものである。全体主義的支配は独りぼっちであること(ロンリネス)の上に、すなわち人間が最も根本的で最も絶望的な経験の一つである。自分がこの世界にまったく属していないという経験の上に成り立っている。
テロルを生む一般的な地盤であり、全体主義的統治の本質であり、そしてイデオロギーもしくは論理性にとっては、その執行者および犠牲者を作り上げるものである独りぼっちであること(ロンリネス)は、産業革命以来現代の大衆の宿業となっていた、そして前世紀末の帝国主義の興隆および現代における政治制度および社会的伝統の崩壊とともに鮮明になった、根を絶たれた余計者的な人間の境遇と密接に関係している。根を絶たれたというのは、他の人々によって承認され保障された席をこの世界に持っていないという意味である。余計者ということは、全然この世界に属していないことを意味する。孤立が独りぼっちであること(ロンリネス)の予備条件であり得る(あらねばならぬ、ではない)のとまったく同様に、根を絶たれていることは余計者であることの予備条件であり得る。それを生んだ最近の歴史的原因や政治の中で、それが演ずる新しい役割を捨象してそれ自体について見れば、独りぼっちであること(ロンリネス)は人間の条件の基本的な要求に背離すると同時に、すべての人間の生活の根源的な経験の一つなのだ。物質的感覚的な所与の世界についての私の経験すらも、私が他の人々と接触しているということに、つまり、他のすべての感覚(センス)を統制し制御しているわれわれの共通感覚(common sense 常識)に依存している。そしてこのコモン・センスなしには、私たちの一人一人は、それ自体として当てにできない不確実なものである自分自身の感覚的与件の特異性の中に閉じ込められてしまうだろう。われわれがコモン・センスを持つからこそ、すなわち一人の人間ではなく複数の人間がこの地球に住むからこそ、私たちは私たちの直接的な感覚的経験を信じることができるのだ。けれども私たちは、自分もいつかこの共通の世界を去らねばならないが、それでもこの世界はこれまでどおりつづいていくのだし、この世界の持続にとっては自分は余計な存在なのだということを想起するだけで、独りぼっちであること(ロンリネス)を、つまりすべてのもの、すべての人から見捨てられているという経験を実感することができる。
独りぼっちであること(ロンリネス)は孤独solitudeではない。孤独は独りきり(アロウン)でいることを必要とするのに反して、独りぼっちであること(ロンリネス)は他の人々と一緒にいるときに最もはっきりとあらわれてくる。これについてはいくつかの感想が散見するが――それらはたいてい《nunquan minus solum esse quam solus esset》すなわち「彼は一人でいたときほど孤独ではなかった」、もっと精確には「彼は孤独でいたときほど独りぼっち(ロンリー)でなかったことはなかった」というカトーの言葉のように逆説的な言い方で言われているのだが――、それらを別にすれば、独りぼっちであること(ロンリネス)と孤独との区別を最初に行ったのはギリシャ生まれの解放奴隷で哲学者だったエピクテトスであったらしい。彼が主として興味を抱いたのは孤独でも独りぼっちであること(ロンリネス)でもなく、絶対的自立という意味で<独り>(monos)であるということだったのだから、ある意味では彼の発見は偶然だった。エピクテトスの見ているように、独りぼっち(ロンリー)の人間(eremos)は他人に囲まれながら、彼らと接触することができず、あるいはまた彼らの敵意にさらされている。これに反して孤独な人間は独りきりであり、それゆえ「自分自身と一緒にいることができる」。人間は「自分自身と話す」能力を持っているからである。換言すれば、孤独において私は「私自身のもとに」、私の自己と一緒におり、だから<一者のうちにある二者>であるが、それに反して独りぼっちであること(ロンリネス)の中では私は実際に一者であり、他のすべてのものから見捨てられているのだ。厳密に言えばすべての思考は孤独のうちになされ、私と私自身との対話である。しかしこの<一者のうちにある二者>の対話は、私の同胞たちの世界との接触を失うことはない。なぜなら彼らは、私がそれを相手に思考の対話を行う私の自己に代表されているからである。孤独が担っている問題となるためには他者を必要とすることだ。私が自分のアイデンティティを確証しようとすれば、全面的に彼らの分裂を解消させ、彼らを思考の対話――この対話の中では人間はあくまで曖昧な存在たるにとどまる――から救い出し、アイデンティティを回復させるからである。このアイデンティティのおかげで、彼らは交換不可能な人格の単一の声で語ることができるのだ。孤独が独りぼっちであること(ロンリネス)になることもある。そうなるのは、私が完全に自分だけを頼りにするようになって、その結果、自分の自己から打ち捨てられているときである。孤独な人々には、彼らを二重性と曖昧性と疑惑から救ってくれる交際という救済をもはや見出し得ないときにはいつも独りぼっちであること(ロンリネス)におちいる危険があった。歴史的に言えば、この危険が増大して人々に注目され、歴史に記録されることになったのは、ようやく19世紀になってからのようだ。孤独というものを一つの生き方とし、仕事をするための条件としているのは哲学者だけだが、その哲学者たちがもはや「哲学は少数者のためにのみ存在する」という事実に満足できなくなり、誰も自分たちを<理解>してくれないと主張しはじめたときに、この危険ははっきりとあらわれてきた。この間の事情をよく物語っているのはヘーゲルの臨終の際のある逸話であるが、彼以前のいかなる大哲学者についてもこういう逸話が語られることはまずないだろう。「ただ一人を除いて私を理解してくれたものはなかった。そしてその一人も私を誤解していた」と彼は言ったというのだ。一方また、独りぼっち(ロンリー)の人間が自分自身を発見し、孤独の対話的思考を始める可能性もつねにある。シルス・マリーアで『ツアラトゥストラ』を発想したときのニーチェにもそういうことがあったらしい。二編の詩(《Sils Maria》と《Aus hohen Bergen》)の中で彼は、独りぼっち(ロンリー)の人間の虚しい期待と憧れつつ待つことを語っている。やがて突然、《Um Mittag war’s, da wurde Eins zu Zwei…/Nun feiern wir,verein》(「時は真昼、そのとき一は二となった……今や祝おう、力を合わせた勝利を信じて、祝祭の中の祝祭を。客の中の客たる、友ツアラトゥストラがやって来たのだ!」
独りぼっちであること(ロンリネス)をこれほど耐えがたいものにするのは自己喪失ということである。自己は孤独の中で現実化され得るが、そのアイデンティティを確認してくれるのは、われわれの信頼してくれ、そしてこちらからも信頼することができる同輩たちの存在だけなのだ。独りぼっち(ロンリー)の状況においては、人間は自分の思考の相手である自分自身への信頼と、世界へのあの根本的な信頼を失うことになる。人間が経験するために必要なのはこの信頼なのだ。自己と世界が、思考と経験を行う能力が、ここでは一挙に失われてしまうのである。
人間の精神の能力で、確実に機能するために自己も他者も世界も必要とせず、経験にも思考にも依存していない唯一のものは、自明性をもってその前提とする論理的推論の能力である。否応のない自明性の基本的原則、2+2=4という自明の理(トゥルーイズム)は、絶対的な独りぼっちであること(ロンリネス)のもとにおいてすらも枉げられることはあり得ない。これは、人間が経験するため、生活するため、そして共通の世界の中で彼らの進むべき道を知るために必要とする相互的な保障を失ったとき、すなわちコモン・センスを失ったときにもなお頼ることのできる、唯一の信頼できる<真理>である。だがこの真理は空虚である。いや、むしろこれは全然真理などというものではないのだ。なぜならそれは何ものをも啓示しないのだから。(幾人かの現代の論理学者のように無矛盾性を真理と定義することは、真理の存在を否定することを意味する)それゆえ独りぼっちであること(ロンリネス)の条件のもとでは、自明性というものはもはや単なる悟性の手段ではなくなり、生産的になりはじめ、それ自身の<思考>の経路を展開させはじめる。どう見ても何らの逃げ道もない厳密な自明的論理性によって特徴づけられる思考過程が独りぼっちであること(ロンリネス)と何らかの関係をもつことは、「人間が孤独であることはよくない」という聖書の言葉についてのあまり知られていない註解の中で、ルターがつとに指摘していることである。(孤独と独りぼっちであること(ロンリネス)について彼自身が嘗めた経験はおそらく何ぴとにも劣らぬものだったろうし、彼は一度「人間には彼が信頼することのできる存在が必要だから、神が存在しなければならない」とまで言った)独りぼっちの(ロンリー)人間は「いつも次から次へと演繹を行い、すべてを最も悪く考える」とルターは言っている。全体主義運動の有名な極端主義(エクストレミズム)は、真のラディカリズムと何らかの関係があるどころか、実はこの「すべてを最も悪く考えること」、つねに最悪の結論に達するこの演繹の過程にほかならないのである。
非全体主義の世界の中で人びとに全体主義支配を受け容れさせてしまうものは、普通はたとえば老齢というようなある例外的な社会条件の中で人びとの嘗める限界的経験だった独りぼっちであること(ロンリネス)が、現代の絶えず増大する大衆の日常的経験となってしまったという事実である。全体主義が大衆をその中で組織した無慈悲な過程は、この現実からの自殺的な脱走のように見える。「君を万力のようにしめつける」「水のように冷たい推論」も、弁証法の「力強い触手」も、何ぴとも何ものも信頼できない世界の中での最後の支点のように見えてくる。それは内的な強制であり、その唯一の内容は一切の矛盾を避けるということでしかない。そしてこの矛盾の回避が、他者との一切の関係の外で人間のアイデンティティを確証するように見えるのである。それは人間が一人でいる場合にすらもその人間をテロルの鉄の箍に嵌めこむ。しかも全体主義支配は、独房に監禁するという極端な場合を除いて決して人間を一人にしておこうとはしない。人間と人間のあいだの一切の空間をなくし、人間と人間とを押しつけることで、孤立のもつ生産的な可能性すらも無に帰せられてしまう。独りぼっちであること(ロンリネス)の中では、すべての過程の出発点にあった最初の前提を取り逃がしてしまったら完全に破滅してしまうことがわかっているのだが、そのような独りぼっちであること(ロンリネス)の論理の働きを教え、それを賛美することによって、独りぼっちであること(ロンリネス)が孤独に変わり、論理が思想に変わるほんのわずかの可能性も消し去られてしまう。このやり方を暴政のやり方と比較すると、沙漠そのものを動かし、無人の地球のありとあらゆる部分を蔽いかねない砂嵐を巻き起こす方法がこれで見つかったというように見える。
《Initium ut esset homo est》――「始まりが為されんために人間は創られた」とアウグスティヌスは言った。この始まりは一人一人の人間の誕生ということによって保障されている。始まりとは、実は一人一人の人間なのだ。
そして「英語版第13章 イデオロギーとテロル――新しい形式」というエピローグを書いています。これも引用抜粋します。
[…]人間と法との同一化は、古代以来の法思想の悩みの種だった合法性と正義との差を解消するもののように見えるが、これはlumen naturale(自然の光)もしくは良心の声とは何ひとつ共通するものを持たない。ius naturale(自然法)もしくは歴史を通じて啓示された神の掟の権威の源泉としての<自然>もしくは<神>は、自然の光(ルーメン・ナチュラーレ)もしくは良心の声を通じて、その権威を人間自身の内面に告知すると考えられているのだが、しかしこのことは決して人間を法の生きた具現にはせず、反対に法は、人間に同意と服従を要求する権威として人間とは異なるものとされていたのである。実定法の権威の源泉としての<自然>もしくは<神>は永遠不易なものと考えられていた。実定法はその時その時の事情によって変化しつつあるもの、可変的なものだったが、しかしもっと急速に変わる人間の営為にくらべれば相対的な不変性を持っていた。そしてこの不変性は、その権威の源泉が永遠に存在することから来ていた。だから実定法は本来、絶えず変わる人間の動きを安定化する要因として機能するよう考えられていたのだ。
全体主義の解釈によれば、すべての法は運動の法則になっている。ナチが自然の法則を、あるいはボリシェヴィキが歴史の法則を語るときには、自然も歴史も人間の行為にとっての安定的な権威の源泉ではもはやない。それらは運動そのものなのだ。自然法則の人間における表現としての人種法則としてのナチの信念の基底には、現生の人間という種ではかならずしも停止しない自然の発展の産物としての人間というダーウィンの観念がひそんでいるが、それとまったく同じく、歴史法則の表現としての階級闘争についてのボリシェヴィキの信念の基底には、それ自身の運動法則に従って消滅する歴史的時代の終末――そこでは歴史の動きそのものが消滅する――に向かって突っ走る巨大な歴史の動きの所産としての社会というマルクスの観念があるのだ。[…]
どちらもかなり抽象的であり、別なことを述べているようでいて、実は同じ文章が出てきます。共通した何かがあると感じました。わたしがアーレントを解説したり要約したりすることはできませんので、あとは各自でお読みになり解釈してください。
それから「独りぼっちでいること(ロンリネス)」について。わたしは独りでいることはまったく平気ですが、自分が「孤立」しているのかどうかはわかりません。確かに、わたしは集団のなかで「独りぼっちでいること」には耐えられそうにありませんし、早く集団のなかから抜けだして「独りぼっちでいること(自分自身であること)」を望みます。そのほうが安心なのです。だからといって、「根を絶たれた余計者的な人間の境遇」「他の人々によって承認され保障された席をこの世界に持っていない」「全然この世界に属していない」という感じがしません。つまり、「独りぼっちでいること」と「孤独、孤立(根を絶たれた余計者)」とは違うのです。
おそらくこれは、コロンバイン高校銃乱射事件や秋葉原通り魔事件と関係があるような気がします。
わたしは組織的集団で仕事をしたことはありません。これは、集団でなければできないことやチームワークの強さを否定するものではありませんが、一方で、集団は個々のメンバーを信頼し合うことが前提条件であり、メンバーを信頼して仕事の悩みを相談したり、「絆」を感じたりすることが、「スムースに仕事ができる」という理想にすぎないことを気づく者は少ないと思います。理想はつねに現実を裏切ります。わたしはこれ(集団行動)が苦手で、しばし独善的だと自分でも思いますが、誰かに相談するくらいなら自分一人で試行錯誤したほうがよほどましです。
これは想像ですが、会社でも家族でも、誰にも悩みを相談できずにいることが「孤独」かつ「不安」で、「自己喪失」の状態かもしれません。
ハンナ・アーレントの思考は、わたしには完全に理解することはできません。共通している感覚があっても勘違いかもしれません。しかし互いに「孤立」していることがナチス集団の残酷な行動の原因であり、その背景を想像するに、「思考停止」「長いものには巻かれろ」などがあったら、それは日本の官僚と同様です。2020年、国内のコロナによる死亡者数は「運命的に」少なかったのですが、そのような「カミカゼ」はもう吹きません。あとは自分たちが考えて政策を出すしかないのです。
(2021年8月21日)