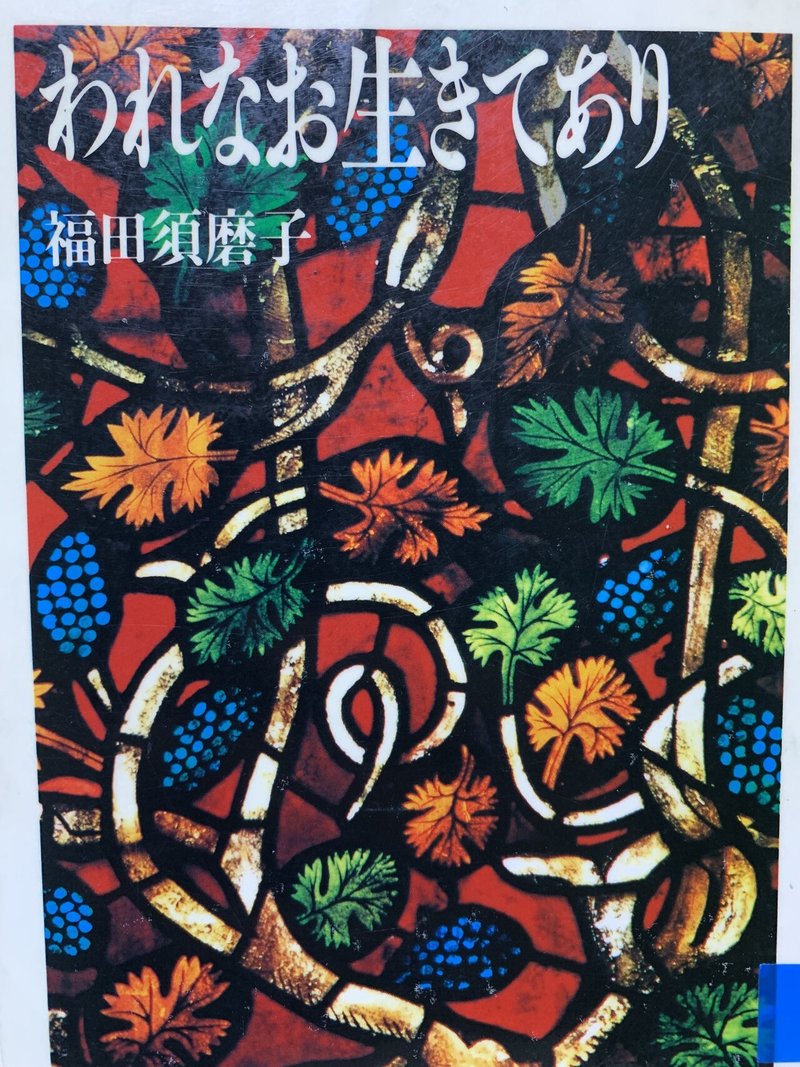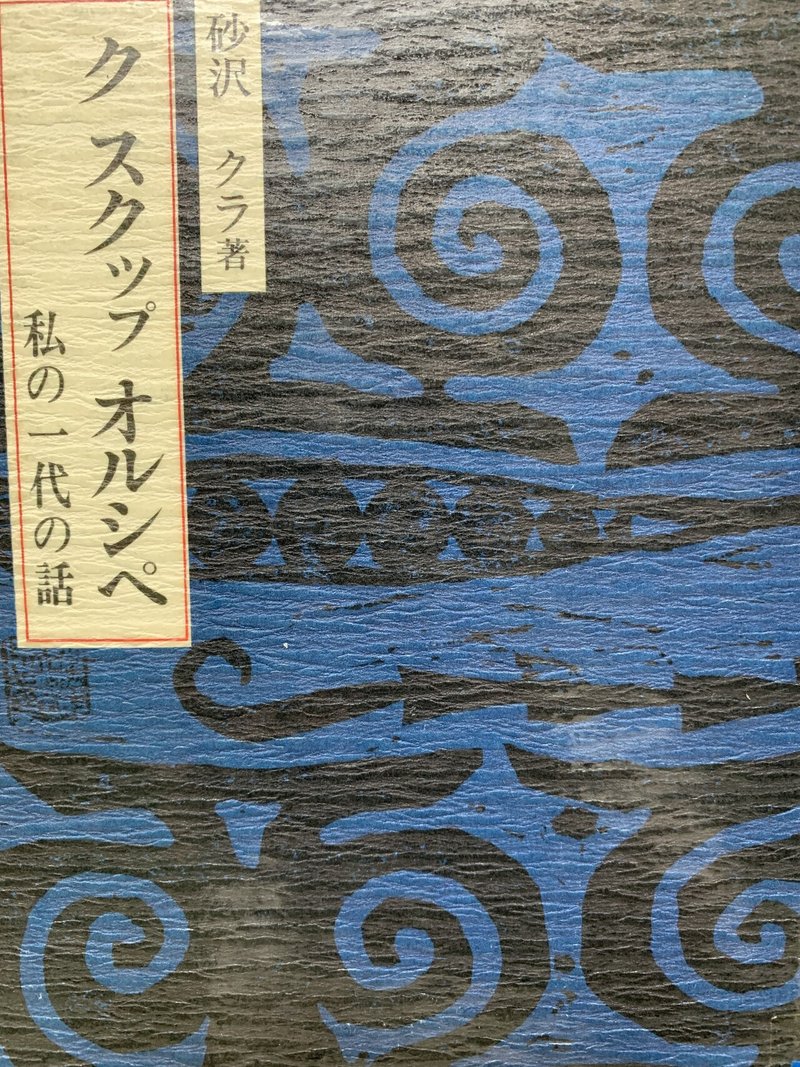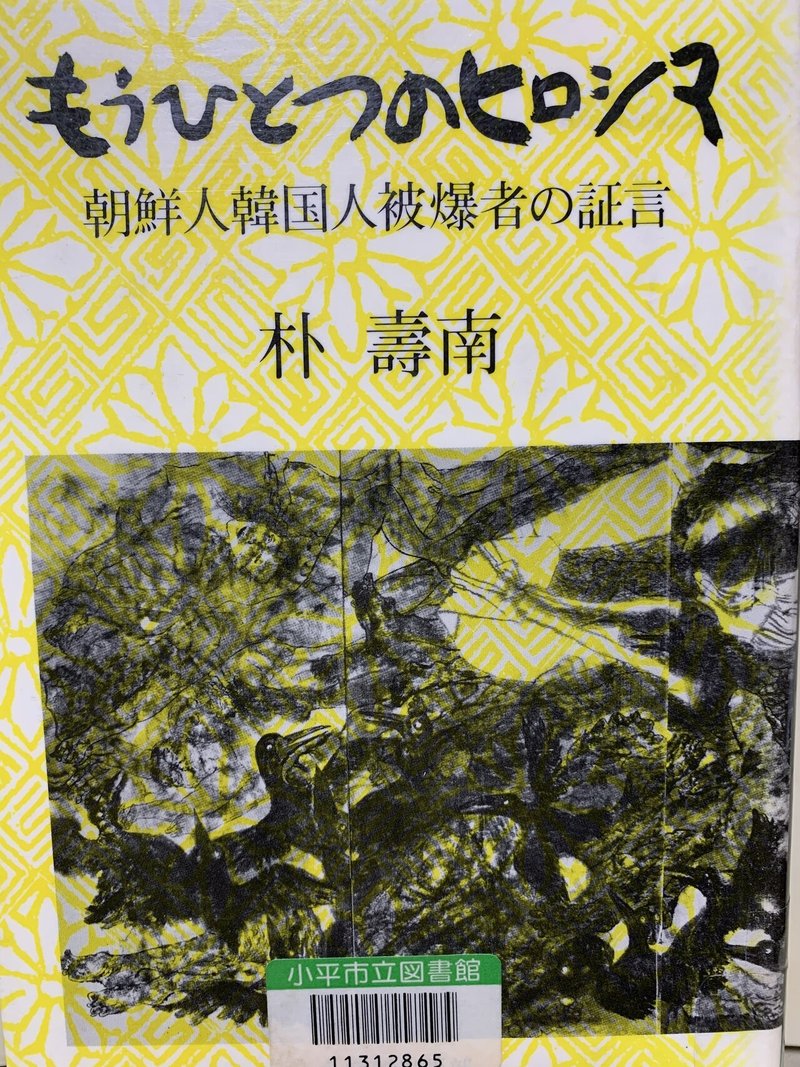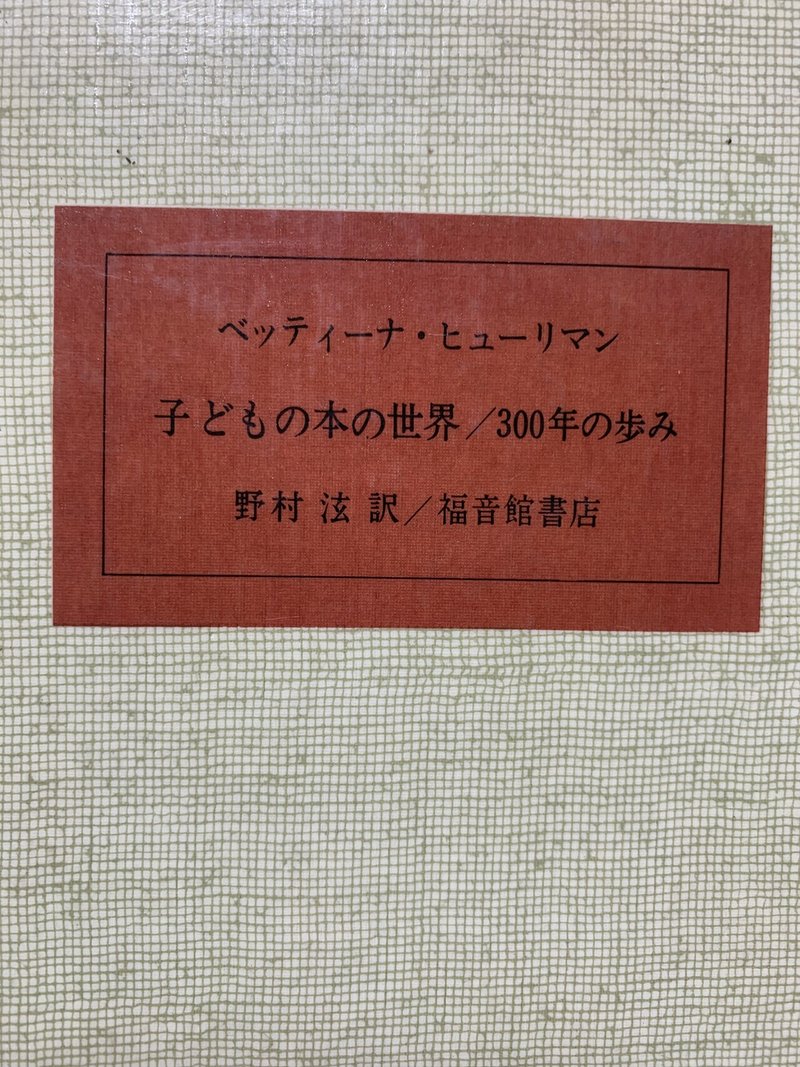本の花束(10)福田須磨子『われなお生きてあり』(1977年、ちくま文庫)
長崎の原爆を題材とした映画や文学はないものかと思い、探してみると黒澤明『八月の狂詩曲(1991)』がありました。原作は村田喜代子『鍋の中(1987)』です。私が無知でした。
広島に原爆が落とされたのは8月6日、長崎は8月9日でした。たった3日とはいえ、「世界で初めて原爆が落とされた国」として圧倒的にヒロシマが有名になったため、ナガサキは比較的影が薄い印象でした。
ところが、長崎県出身の福田須磨子がおりました。須磨子は当時23歳、勤務中に被爆します。自宅にいた両親と長姉は被曝死しました。翌年、高熱、疲労感、脱毛の症状が出、10年後、エリテマトーデスを発症。病床のなかから詩を綴り、『詩と随想・ひとりごと(1956)』、『原子野(1958)』、『烙印(1963)』を発表しました。原水爆禁止運動に積極的に関わるようになり、自伝小説『われなお生きてあり(1967)』を出版します。
八月八日――その前日、父との会話でこんなことがありました。「サイパンが敵の手に渡ってからこっち、ずっと負けいくさやがね、転進、転進って何ね、ずっと退却ばかりやかね、東京でも大阪でも滅茶苦茶やられても損害軽減って嘘ばかりやかね、沖縄も地形が変わるごとやられてしもうて、いよいよ日本に上陸するかも知れんと言うところまで追いつめられとっとやろがね、勝ちよっと(勝っている)なら、こんげんことになるもんね」と父が苦々しげに言い、ゴザの座布団の下から、気味悪そうに一枚の紙をつまみ出して須磨子に渡します。色刷りの小さなビラに、日本の地図が中央に書かれ、上のほうには時計の絵が書いてあり、「さくら三月花ざかり、八月日本は灰の国」というような文句が書かれていました。
[…]今日は十二日、原爆がおちてから三日目である。誰が言い始めたのか、皆原爆のことをピカドンと言うのが耳につく。そのものずばりの表現に違いないが、どうも私はこの言葉に抵抗を感じる。そのおどけた語呂のもつ語感が被爆者のみじめさを自嘲し、茶化しているような感じがして、やりきれないのかもしれない。ピカドンという言葉はその後、長い間、使われたが、意固地な私は一度もその言葉を口にしなかった。「原子爆弾」という、妙に重々しいこの呼び方の方が、私の悲しみと苦しみを表現するものとして適切なひびきを持っているように思われるからである。
被爆した人たちは、全身黒焦げになって死んでいたり(焼けた皮膚が縮み上がって腕や脚が宙に浮いてみえる)、片側半分だけ火傷をしたり、川や水がある場所では、みな水を求めて折り重なるようになって死んでいたりします。一瞬で焼け焦げるのですから、おそらく喉が渇いてしかたがないのでしょう。顔が能面のように膨らみ、誰の顔だか判別がつかなくなります。
なかには無傷に見える人も、急に発狂死したり、紫色の斑点が皮膚にあらわれて、いずれ亡くなっていきます。広島も長崎も「原爆症」の症状は同じです。
須磨子は原子爆弾の後遺症と生活の困窮に耐えながら、1974年、52歳で亡くなります。原爆投下後の広島の状況を急いで書いた『半人間』の大田洋子と違い(そして彼女は「原爆作家」と呼ばれることを嫌がりました。原爆直後の報告をしたのは作家の<使命>であって、人びとは「原爆で儲けている」と邪推したからです)、福田須磨子は被爆後およそ30年もの間「生きて」きたのであり、小説として結晶化しました。想像力を使って描いた小説とはまた違ったものですが、細部まで生々しくて重いこの作品こそ、ぜひ映像化してほしいものです。
(2021年8月8日)
本の花束(9)砂沢クラ『ク スクップ オルシベ――私の一代の話』(北海道新聞社、1983年)
私が20~30代のころ、新宿二丁目に行きつけのバーがありました。あるとき偶然、宇梶剛士さんが店に入ってきました。宇梶さんはマスターに電話して事前に確認し(お客さんが少ないときに店にやってきた)、バーのカウンターの隅っこで、大きな図体を縮こませながらひっそりと飲んでいました。レディース・バーですから、これくらいの気遣いは現代なら当たり前ですが、20年前はできない男性がほとんどでした。多くの男たちは土足で踏み込み傍若無人に振舞うのが男らしいと勘違いしている一方で、宇梶さんは、靴を脱いでそっと上り込み、隅のほうでじっと正座しているようなものでした。バーにはバーの作法があり、宇梶さんはその作法をちゃんとわかっている人でした。
宇梶さんはアイヌ人の血統を持っており、かつては暴走族の総長でした。そんな話をどこかで聞いた覚えがあり、「やっぱりマイノリティは違う」と私は関心しました。
もう一つ、私の思い出話があります。小学校低学年のとき、遠足か校外学習で登別の観光地に行きました。そこでアイヌ人が民族衣装を着て踊ったり歌ったりしていました。誰かが「アイヌ人は仕事がないからしかたなく観光でやっている」と言いました。みやげ物は織物や染物、ムックリなどの民芸品でした。
砂沢さんの本を読んだとき、まるで神話の世界だと思いました。山に入ってはクマや鹿を撃ち、川に入っては鮭やマスを捕まえます。ヒグマやシマフクロウ、シャチを殺す「イヨマンテ(クマ送り)」と呼ばれる儀礼があります。和人(シャモ)は「アイヌ人は無知で野蛮だ」という偏見があるので「動物を殺す残酷な儀式」と一方的に決めつけますが、本当は動物を殺してその魂であるカムイを神々の世界(カムイ モシリ)に送り帰す祭りを意味しています。狩猟民族であるアイヌは、生きた動物を神聖視していることがわかります。ところが、砂沢さんが成長するあいだに「アイヌ地問題」が起こり、狩猟民族から農耕民族に強制的に変えられてしまいます。砂沢さんは「アイヌ民族の悲劇」を体現したのです。
1991年、戦後生まれのアイヌ女性チカップ美恵子さんが『風のめぐみ――アイヌ民族の文化と人権』(御茶ノ水書房刊)という感動的な文集を出版しました。その本でチカップさんは、和人によるアイヌ絶滅政策の歴史を追及しつつ、同時に現在のアイヌ差別(主に就職や結婚、“旧土人保護法”など)と、そして“開発”の名の下での「アイヌ モシリ(人間の大地)」の破壊への怒りを書いています。かつてイギリスの女性旅行家イザベラ・バードが「筆舌に尽くしがたいほど美しい森や山や川」と驚嘆したアイヌの聖地・二風谷(にぶたに)や沙流川(さるがわ)は、いま、ゴルフ場やダムの建設によって水底に沈められ、汚されようとしています。
チカップさんたちは、アイヌの人権をたたかいとるために、アイヌ文化をルネッサンスに向けての作業を展開しています。刺繍、歌、踊り等を中心にして。和人はアイヌ民族を同化させながら滅ぼそうとしています。そして、こうしたチカップさんたちのルネッサンス運動を可能にした土壌を、それこそ地底から支えてきたのが、1983年に刊行された『ク スクップ オルシベ――私の一代の話』の著者・砂沢クラさんのようなアイヌ女性です。砂沢さんのような人がアイヌ女性であったためのとてつもない辛苦と悲哀に耐えながら、民族の精神と文化を誇りをもって守り通してきたからです。
著者は1897(明治30)年生まれ。この本は、87歳に至るまでのアイヌ女性のながい生の歩みの一つ一つを、書き溜めていたノートと絵をもとにして克明に物語ったものです。「ア、イヌが来た」という愚弄に象徴される人生の牢獄のなかで、砂沢さんはユーカラや伝統工芸を継承しつつ生き抜いたのです。
この本を読みながら、わたしは登別の出来事を思い出します。アイヌ民族の伝承のためと謡いつつ、アイヌ民族を見世物にしている、と。
(2021年8月6日)
本の花束(8)朴壽南『もうひとつのヒロシマ 朝鮮人韓国人被爆者の証言』(1982年、舎廊房出版部)
詳細は省きますが、「平和の少女像」などを展示した国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」内の企画展『表現の不自由展・その後』が、開催から3日間で中止に追い込まれました。いまから3年前の出来事です。「ガソリン携行缶を持ってお邪魔する」と書かれた脅迫ファックスなどが届き(2019年京都アニメーションガソリン放火殺人事件を彷彿させる)、安全面に気を配ったといいます。慰安婦問題を扱う作品のほか、憲法9条、昭和天皇や戦争、米軍基地、原発、人種差別などのテーマ性を含む作品が並んでいました。
日本人はえてして「政治的中立性」を保つ人たちです。良く言えば「不都合には決して触れない」人たちのことで、悪く言えば「議論できない」人たちのことです。つまり、反対意見を持つ人たちを攻撃してしまうのです。たとえるならば、妻や子どもが反論すると、言葉ではなくつい手が出てしまう、頭の悪い暴力夫のように。能力もないのに、夫の威厳や面子を保ちたい。そうなると、歪みは必ず弱い立場に悪影響を及ぼします。人間関係でも国際関係でも同じです。
なぜかというと、わたしは本書で知ったのですが、軍部広島がヒバクシャ・ヒロシマと化したのは周知のことで、朝鮮・韓国人被爆者が相当数いたことも事実です。日本は被害を受けたことは大声で言いますが、同時に加害者であったことは一切沈黙します。謝罪したくないし、責任を負いたくないからです。
個人的経験からいうと、わたしにはリハビリ担当の人たちがいます。身体を動かすのと同時に、積極的に話をして言語のリハビリもしようとわたしは思いました。
その担当者は同世代の人で、最初はわたしも「話が合うかも」と思いました。ところが朝鮮・韓国人のことになると、とたんに「あいつら識字率ゼロパーセントだから!」と軽蔑を込めて担当者は言いました。驚いたわたしは「どうしてそんなことを言うのか? 親から教わったのか?」と責めました。担当者は仕事を忘れて、わたしをやりこめようとしました。言葉がまったく出てこないわたしはひどく憤慨し、すぐに担当者を辞めさせました。わたしがもう少し冷静だったら、朝鮮・韓国人を差別する人の気持ちをちょっとでも理解することができたのに、と後悔しました。
しかし、差別発言する人をわたしが理解する必要はない、差別発言は無理解のうちに発するものだから、と思い直しました。なぜなら「差別発言する者は己の劣等感が表れている」からです。
悲痛極まりない、人間を根底から打ち砕くむごい本当の悲劇は、多くの場合、同時に悲劇の当事者がそれについて語ること自体すらも不可能にしてしまう苛酷さをともなっています。まさに、生き残った広島・長崎の朝鮮・韓国人被爆者の場合がそうでした。
日本原水爆被害者団体協議会が被爆者13000人を対象に行った膨大な調査の記録、『ヒロシマ・ナガサキ 死と生の証言――原爆被害者調査』(新日本出版社、1994年刊)は、原爆が被害者に対して「人間として死ぬことも、人間らしく生きることも許さない」、反人間的被害を身体にも心にも今も与え続けていることを訴えています。しかし、「韓国人原爆犠牲者慰霊碑」(1970年4月除幕)が、広島の平和公園の外に押しやられている事実に象徴的に示されているように、朝鮮・韓国人被爆者は、被爆者差別とともに民族差別があり、また、民族分断の悲劇もからまって、日本人被爆者よりもさらに、人間として死ぬことも、人間らしく生きることも許されない生の苦しみのなかに閉じ込められてきました。しかも、死者4万人、負傷者3万人といわれる広島・長崎の朝鮮人被爆者のことは、その事実も知らされず、日本の反核平和運動のなかでも、生存者や遺族の存在は長くとりあげられることがなかったのです。
そして、朝鮮・韓国人被爆者の幾重にも折り重なった悲痛な悲劇と苦悩は、「同胞たちはわが子にさえ『ピカにおうたこと』を話すこともなく、訴えることばも、相手をも持たずに、……沈黙の闇に生き埋めにされていた」と、本書のなかで著者が記しているような情況をつくり出していたのです。
1965年、広島、大阪、筑豊、対馬、新潟などへと、在日同胞の現実の姿を求めて歩いた朴壽南(パクスナム)さんは、広島の被爆者同胞と出会い、「沈黙の闇に生き埋めにされている」その存在を知り、そして、「非在としてあるもう一つのヒロシマの復権」のために、被爆者同胞からの聞き取りと、強制連行による徴用や学徒動員、そして徴兵など軍部広島の苦役に繋がれた朝鮮人の歴史を追究する作業に全力を傾けます。失業対策現場やいまはなき<原爆スラム>で、朝鮮・韓国人被爆者と寝食を共にして。
しかし、被爆したこと自体を他人に知られたくないために「原爆手帖」も取ることもできない人たちが、簡単に自分の体験を語ったりはしません。朴さんはこう記しています。「生活と生命の崩壊の過程で、人びとの魂もまた深く傷ついている。現実に悲惨の極を生きている同胞たちは、寡黙である……。そして、外の人間が決して踏み込むことのできない奈落の底に、声もなく、うずくまっているのだろう……。それらの人びとの沈黙を打つ資格がわたしにもあるのか……。生あるものの絆から絶ち切られている死者のように、打ち棄てられている同胞たち……。あるいは、血しぶきをあげる狂気の夫や、妻たちの修羅葛藤の現実に、そして、その子供たちの引き裂かれた絶望的な魂に――。これらの人びとが持っている唯一の自衛の手段は、沈黙だけではないだろうか」と。
本書は、1972年に刊行された朝鮮・韓国人被爆者証言集『朝鮮・ヒロシマ・半日本人――わたしの旅の記録』(三省堂刊)の増補改訂版ですが、作業開始から十年後に非常な困難をのりこえてこの証言集を完成させることができたのは、なにより朴さんが、悲劇的沈黙への深い感受性と想像力をもった女性だからでしょう。本書をはじめとする朴さんの作業のすべては、<声>を存在させる闘いでした。他者の沈黙をみつめ抜くことができない者に、<声>を存在させることはできません。朴さんの本から視えてくるのは、朝鮮・韓国人被爆者の存在だけではなく、同時に、悲劇を生み出した日本というものの姿です。そして、その姿をみつめ抜く以外に、いま、日本の未来への道はないのです。本書はけっして忘れてはならない本だと、わたしは思います。
(2021年7月27日)
本の花束(7)「カミーユ・クローデル」(レーヌ・マリー・ハリス、エレーヌ・ヒネ、1989、みすず書房)
フランスの女性彫刻家カミーユ・クローデル(1864~1943)は、ロダンの弟子であり愛人であり、また詩人ポール・クローデルの姉でした。彼女はたぐいまれな才能と美貌に恵まれ、ロダンとポール・クローデルという二人の芸術家に深く霊感を与えながら、自らは精神に変調をきたして創作活動を挫折しました。そして30年間もの年月を精神病院で過ごし(カミーユ48歳のとき強制的に閉じ込められた)、孤独のうちに一生を終えたのでした。この事実の残酷さは、あまたの議論を呼び起こしました。入院がはたして適切な処置であったか否かが問われ、また、彼女を病院の壁の彼方に遠ざけ、世のなかから忘却させたのは陰謀であるという主張もなされました。運命に呪われた芸術家といったイメージと、30年間死んだも同然の生活を送った彼女の、病気に関する医学的情報の少ないことも、さまざまな憶測を生ませ、彼女の真の姿を曖昧にし、議論をますますエスカレートさせる原因ともなりました。
クレペリンは1899年の論文でパラノイアという疾患を初めて定義しました。彼は、内的ないくつかの原因にもとづき、妄想が次第にゆるぎないシステムを構築・発展していくにもかかわらず、思考、意思、行動などのまとまりと精神の明晰性は完全なままで残されているケースに限って「パラノイア」と呼ぶことにしました。パラノイアの存在そのものは、フランスでは1852年にラゼーグの発表した『被害妄想の研究』によって、つとに知られていました。
クレペリンはこのパラノイアを、基礎とその上の構築物の二つの部分に分けて考えたのです。彼は記憶の錯覚(イリュージョン)が出発点で重要な役割を果たし、妄想はそれに続いて現れるとしました。クレペリンは、患者が周囲の人間のしぐさや言葉、あるいは日常生活のなかで知覚する形象や象徴を、どのように極介していくか、を記述しました。
フランスではセリューとカプグラが《解釈》という視点から、症状をすばらしい文章で記述し、“解釈妄想”として、病気の特徴を説明しました。
彼らによると、解釈妄想は組織化された妄想が主体となった慢性の精神病で
1 妄想が多様で、体系化されていること
2 幻覚やそれに近い現象の見られること
3 明晰で他の精神能力が保持されていること
4 解釈がどこまでも進行し、拡大する傾向のあること
などの特徴があるとしています。
カミーユ・クローデルのパラノイアがいかに形成されたかを理解し、その核心に迫る作業を、次のような順序で進めることにします。
1)まずカミーユの生活史のなかで、精神的外傷となったとみられる事件
2)彼女の性格、パーソナリティー
3)妄想の出現と、それに関する病院に残された資料
1)事件、精神的外傷、葛藤
そもそも彼女は、生まれたときから母親にとってのぞましい子ではありませんでした。変わった始まりではありますが、当時はよくあることでした。彼女の生まれる16か月前、両親は幼い息子シャルル・アンリを失って悲しんでいました。母親のクローデル夫人にとって生まれてくる子カミーユは、この死んだ息子の代わりの男の子であってほしかったのです。
そして、それまで表に現れなかった夫婦の不和がそのころから急に目立つようになりました。カミーユは、こうしたケースでしばしば見られるように、夫婦のあいだで引っ張り合いになる代わりに、たがいの争いの道具に使われます。彼女が父親っ子になり、父親の自慢の種になればなるほど、母親からは疎まれ、邪険な扱いを受けがちでありました。そこにメロドラマによくあるように、妹ルイーズが生まれました。そして母親のお気に入りになります。
その結果、二人の姉妹は感情的にはげしいライバル意識を抱き合うようになりました。子どもたちは親の争いに巻き込まれ、華々しく悪口雑言を投げつけ合いました。カミーユと弟は、この暴力的な闘争の雰囲気を逃れ、独立を求めてたがいに接近するようになりました。しかし彼らの関係も、彼らが観察してきたものと同じ暴力で染まることになります。あらゆる環境でみられる現象ですが、観察されたものは観察してきたものなかに徐々に浸透していきました。
カミーユはすでにポールに支配力を働かせていましたが、彼女はポールの愛を独占し、彼を自分の支配下に置こうともくろみました。さらに、母方の祖父であるアタナイーズ・セルボーが死んだとき彼女は17歳でしたが、彼女はこの祖父になついていたのでこの死のショックが大きく、悲しみの度合いはまさに《喪の反応》でありました。
以前から、彼女は(自分の意のままになる)土や粘土をこねるのが好きでしたが、そのころから彫刻を始めました。それは母親の拒否反応に出会いました。二人のあいだの新しい行き違いの種です。他方で、彼女は父親から(金銭的に)密かに励ましを受けていました。この父は母親が反対したり禁じたりすることをやるように、娘をけしかけているのでした。これが、因習に逆らう傾向をカミーユに植えつけたのです。
同様に、ロダンの弟子であると同時に愛人であるという二重の関係を、カミーユが、どうして傷つくことなしに通り抜けられたでしょう。真偽のわからないことがらはいくらもあります。ロダンが彼女のアイディアを盗み、彼女の仕事を自分の作品として横取りしてしまったという話は、どこまでが事実か曖昧ですが、ロダンが21歳の乙女の肉体と青春を奪ったことは否定しがたい事実です。
また、いま一つ明確さが欠けていますが、1893年の流産、1896年あるいは1897年に、彼女がロダンの二人のモデルか下職人から受けたとされる迫害が続きます。自身の才能や自主性を認めてもらうことができず、世間的にロダンの弟子としか認めてもらえない立場にありました。
そして1898年彼女が34歳のとき、13年にわたった波乱に富んだロダンとの情熱的な愛の破局となりました。女性としての生きかたの失敗を認めて、みずからの女性らしさ(フェミニテ)を放棄しますが、それは芸術創造の分野では自殺にひとしい決意です。当時の人間の目から見れば、この破局は彼女の職業生命を断つことをも意味していました。そして事実、そのとおりになったのです。しかし、それは彼女の精神病の病状がそうさせたのです。
われわれは人生の刻一刻とその結果を別の観点から観察しなければなりません。つまり一人の人間の過去の行動のすべての《なぜ》を、未来に影響を及ぼしうるものとして理解しなければなりません。カミーユ・クローデルの生涯には精神の外傷をもたらしたに違いない(あるいはもたらしえた)有害な情況、事件、環境との相互作用といったものが、探せばいくらでもあるのは事実です。家族をめぐる環境もあれば、女性としての生活、彫刻家としての創造力を開花させることのなかにもありました。その全体が、どこからでも糸をたぐればたどりつけそうな興味深々たる織物を作っています。
しかしカミーユの入院の説明をすべてそこに求めるのは無理です。せいぜい、彼女のパーソナリティーや人生を屈折させる要素となっただけです。どのようにこじつけようと、それを彼女のパラノイアあるいは彼女の行動異常の、直接の原因とは認めがたいのです。ことはそう単純ではありません。どれほど多くの人間が、彼女と似たような情況、あるいはこれよりひどい情況を生きたでしょう。にもかかわらず彼らはパラノイアにならずにすんだのです。
2)性格特性
カミーユの性格特徴を描いた証言は、こまかなところまで一致しています。彼女はきびきび決断し、批判精神の強い子どもでした。彼女はすぐ反抗的になり、家族のなかで自分の意見を押し通しました。思春期の時期は、誇りが高く短気で、疑り深くかつ頑固と評されています。彼女は自分に権利があると思うなら、ほんのわずかなことも譲ろうとしませんでした。
ロダンとの関係を通じて、彼女は愛情面でも独占的なところを示し、要求が強く、しばしば荒れ狂うこともありました。ベルナール・シャンピニュエルは、ロダンについての著作のなかで書いています。《カミーユの恋の狂乱ぶりはしばしば悲劇的な趣を呈した(1890年においてすでにそうであった)。彼女は他と分かち合うことなど絶対に認めなかった。彼女の苛立ちは激しくなり、ついには病的なそれに近くなる。彼女は、自殺を口走るようになる》。
ロダンとの破局の後、人間不信になり、疑惑を抱き、自分を脅かすと感じられるものすべてにたいする、耳障りなほどの当てこすりが目だってきます。
これらの性格的な特徴をみて、彼女にパラノイアの素質があったといいきってよいのでしょうか。それはちょっといいすぎでしょう。後に古典的な考えかたになる、彼女の自尊心と疑い深さと精神的な柔軟性の不足とを結びつけて肯定する者もいますが、それは言いすぎでしょう。それより、パラノイア傾向をもった性格というのが妥当です。それがカミーユのその後の生活や出会いの影響で急激に極端になっていくのです。この流れのなかで不可避的に、パーソナリティーの構造が固まり、もとに戻らなくなりました。そして精神病としてのパラノイアが、妄想をくすぶらせ始めます。妄想は、さまざまな場面でちらちらと見え隠れするようになります。そして、それが次第に彼女の精神全体を占領するようになっていきました。
カミーユ・クローデルは美しい人でした。端正な顔形と繊細な表情が印象的であり、大きな青い目には奥深いところからさしてくるような光があり、みなぎる力を感じさせました。
しかし、それは彼女の非常に若いころ、つまり彼女がロダンのアトリエで働いた時期だけの真実でした。それは長くは続きませんでした。1897年の日付の入った一枚の写真がペルセウス像を彫刻中のカミーユを写しています。
彼女はまだ33歳になっていませんでしたが、すでに太っており、顔は二重あごになり、むくんだ感じでした。時とともに、この傾向はさらに進みました。彼女はずんぐりしてきて、表情も鈍重になります。
ロダンとの決別後に撮られた、彫刻用の盤と金槌を手にした写真では、彼女は《男おんな》ふうの風貌を見せています。今世紀の初めごろの写真には、生活の苦しさからも来ているのでしょうか、もはやかつての面影は目にしか残っていません。周囲の人間には、わずかのあいだに十歳も年をとったようにみえました。
この外見の変化から、あまり多くの憶測をすべきではありません。ロダンのアトリエでは下職人のあいだでごく《当り前》のようにぶどう酒が乱用されていました。カミーユもかなり飲むほうでありました。彼女の顔のむくみは、むしろ飲み過ぎを思わせます。しかし、栄養や遺伝的体質などの要素も考えられます。後に入院したとき、彼女は自分から食事を断ったために痩せたという証言があります。そうあって当然でしょう。しかしカルテには、特にそれに関した記載はありません。規則的に、身体面では《健康は良好》、あるいは《満足すべき状態》とのみ書かれています。
3)精神病とパラノイア
1913年3月7日、医師ミショーは、この章の後半に写しを載せたような診断書を書きました。カミーユは、《ロダン一味》に迫害されると怯え、部屋を内側から密閉したため息苦しくなるほどでありました。毒を恐れ食事もとらず、必死に心身の安全を守ろうとしていました。それは見るにしのびないほどひどい生活でした。時に48歳。それから彼女は精神病院で一生生活を続けるようになります。一般の例にもれず、入院の措置が取られたのは、病気の最初の症状が現れてからかなり経ってであり、見る人を茫然とさせるほどひどい状態に陥ってからです。
1989年から1904年にかけては、伝記的な資料も欠けており、カミーユの考えの変化をたどること、つまり、彼女の理性が妄想のほうにどのようにずれこんでいったかを示す初期の兆候を探しだすことはできません。
1905年の11月に精神異常があったのは明白です。彼女は、ふたりの男がよろい戸を壊してなかに入ってこようとしましたが、その二ふたりが、ロダンの命令を受けて彼女を殺しにきたイタリア人のモデルだとわかったという話を、これは秘密だと断ったうえでアスランに打ち明けています。彼女は明白でした。彼女はロダンにとって邪魔だったのです。だから彼が彼女を消そうとしたのです。
それから1か月後の12月、彼女の回顧展の二日目、ユジェーヌ・プロの家で、カミーユは突然に怒り出して、いあわせた人々の眉をひそめさせています。こうして彼女はそれまで親しくしてくれていた友人や親類との関係を断ち切ってしまいます。近親者たちも、彼女の常軌を逸した行動と粗暴で無作法な振る舞いにはついていけなくなります。それらは理解しがたいというより、受け入れがたいものでありました。
それに続く1906年初の数か月、彼女は徹底して自分の彫刻作品を壊してしまいます。精神異常のなせるわざと見てよいでしょう。彼女は、ロダンの影響を示すもの、ロダンの存在を感じさせるもの、ロダンといっしょに過ごした時代を思い出させるものすべてに自分をぶつけ、それを破壊しつくそうとしたのです。そう解釈しても大胆過ぎる推理とはいえません。
弟ポール宛に書かれた手紙には、ロダンが彼女の作品を盗んだという訴えがくどくどくどくど繰り返されています。被害観念? それにはまちがいありません。自分を守るために相手を攻撃する、いわゆる迫害された迫害者の例です。他の例では、迫害者に変わった暴力は目を見張るほど激しいものですが、彼女の場合さほどではないのは、女であるという条件のせいでしょうか。
妄想のテーマは、ロダンに集中しているのがはっきり見てとれます。すべての妄想がそうであるように、現実にぴったり合う部分はひじょうに少ないのです。カミーユには天才がありました。彼女がロダンの作品や人間そのものに惹かれたことは容易に想像できます。彼女がロダンのために働いたことも確かです。彼女は彼から学ぶことも多かったでしょう。しかしそこから、ロダンに盗作された、不当に下職人扱いをされた、さらには、彼の好敵手になったから(彼の地位を脅かすに至ったから)迫害された、彼女が邪魔になってきたから、ロダンは殺し屋を雇って彼女を殺し、厄介払いしようとしたと主張するにいたっては、常識的には受け入れられません。
カミーユは現実の比喩的解釈から出発し、純粋に思考の産物にすぎない妄想にたどり着いたのです。しかし、カミーユにとってはそれは比喩ではなく、ありありとした現実であり、確信であり、いかなる反論にも揺らぐことがない、疑う余地のない真実だったのです。
ロダンの行動が、彼女の解釈とは正反対であることを示す事実がいくらかあったとしても、そんなものは嵐のなかのわらくずのように、妄想の勢いに吹き飛ばされてしまったでしょう。
読者のなかには、わたしが《カミーユのもっとも熱心な支持者たちも、妄想だと見破れたはず》と書くのを予想した人がいるかもしれません。しかしそう書かなかったのは、もちろん意識してのことです。妄想患者の確信の力は、強い感情のエネルギーが込められ、また本人も見たところ非常に論理的なので、しばしばまわりのものは妄想の航跡のなかに《魅入られた》とでもいいましょうか、引き込まれてしまうのです。感情の盲目的な大波を前にして、理性の力がいかに微々たるものかを見せつけられるのは心の痛むことです。
《永遠の昔から続く理性との闘いで、感情が負けたことは一度もなかった》(G・ル・ボン)。それどころか妄想患者に説き伏せられ、妄想に積極的に加わり、それを強化していくものさえ出てくるのです(フォリー・ア・ドゥ:二人狂い)。
カミーユ・クローデルの精神療養所生活は、1913年3月10日ヴィル=エヴラール病院で始められました。1914年9月5日から7日のあいだ、彼女はモンドヴィルグ療養所に移され、1943年10月19日に死亡するまでずっとそのままでした。手続き的にみると《形式上の自発入院》です。この形式はいまも昔もありますが、まずは妥当でしょう。《強制入院》より厳しくはなく、取り消すこともより簡単にできる、ずっと柔軟な措置です。しかし、入院を必要とする症状は、どちらの場合にも変わりはありません。この自発入院には、精神状態の詳しい記載のある、自他に傷害を加えるおそれがあることを示す診断書と、家族の同意が必要です。家族がいなければ責任ある近親者の一人が入院に同意しなければなりません。それ以後も、入院を継続させようとするなら、非常に厳しい規制にしたがって行われなければなりません。正式の診断書が求められ、検事の検閲も行われます。
カミーユは合法的手続きのもとで入院させられました。ミショー医師の診断書もあり、入院を要請する書類に、当時、すでに未亡人になっていた彼女の母のサインもあります。この母が多少とも無意識的に娘に対して攻撃的であり、カミーユが芸術の世界で仕事をすることに反対し、彼女の私生活をけっして認めようとしなかったのは事実ですが、実の母親が娘を入院させようとやっきになり、悪意をもって進んで書類にサインしたという主張に誰が納得できるのでしょう。医学に縁のない一般人だって、入院直後、療養所の医長――現在は精神科の医長――が患者を診察し、入院の措置が必要であったことを確認する診断書を書かねばならぬことくらい知らないはずはありません。
当然のことですが、医師たちの名誉のために敢えて断っておきましょう。カミーユが戦争の事情でモンドヴェルグに移されたとき、療養所の医師は、ただ新しい滞在者を受け入れればよかったわけではありません。彼は入院の措置が正しかったかどうか調べ直す義務を負わされていたのです。1914年9月22日付の診断書はそのためのものです。そのなかでプロゲール医師はカミーユが《まちがった解釈と空想にもとづいた、組織化された被害妄想をもっている》と証言しています。カミーユがロダンと別れてから、すでに16年経っていました。
療養所のなかに保護されていたにもかかわらず、彼女があいかわらず恐れていたのは、《ロダン一味》による毒殺でした。彼女は看護師が、彼らに便宜をはかっていると非難しはじめました。彼女は自分の食事は自分で作らせるように要求しました。その当時は、このような症状に有効な薬はまだ何ひとつ知られておらず、彼女が何らの投薬を受けていなかったことを忘れてはなりません。薬が投与されるいまの時代とは違い、たとえば彼女は自分の飲まされている薬が実は毒なのだと、主張を正当化する状況にはなかったのです。
毒殺の恐れが常にあるという主張は、具体的な実行の手段が考えられていない限り、妄想的産物の証といってよいでしょう。彼女の生涯の不幸な一連の事件から説明可能だとして、カミーユのとった行動を説明しようとする試みにも同意できません。それらの事件は確かにある役割を果たしています。
しかしそれが妄想の原因だと見るのは間違いです。妄想の原因となることと、妄想の形を決めたり妄想の材料に使われることとは次元の違う問題で、混同されるべきではありません。カミーユの作品が盗まれたという場合、それは比喩的な表現では言いえましょうが、毒殺というテーマは、そのような比喩的な表現とはまったく関係がありません。そこには確信があり、それが人間の情緒的な全エネルギーを吸い上げて、純粋に精神的産物にすぎない観念のなかに注ぎ込むのです。
このような場合に《強迫》という言葉が使われるのを耳にします。《彼女はいつもその問題に戻ってくる……その話しかしない……彼女は、どんな行動をするときも、その考えが頭から離れない……彼女の強迫観念ね》。
しかし、ここで用いられている強迫観念という言葉は医学用語のそれではありません。《強迫観念》は、精神医学的には妄想とはまったく違った症状を示す言葉です。強迫観念は、本人がばかばかしいと思っているのに、どうしても追い払えない考えのことです。患者は自分の考えがそちらに向いてしまうことに苛立っています。それが異常な現象だと自覚しています。
もっとも一般的なのは不潔、とくに細菌にたいする恐怖です。患者は手を洗います。その手を拭いたタオルを洗います。手を汚さないように手袋をして洗います。そして、それをまた洗うといった具合です。強迫神経症の一番思いものでも、妄想とは無関係です。生活するうえでは、強迫観念のほうがかえって苦痛な場合もありますが。
カミーユの妄想は1904年ごろ目立つようになりました。妄想を抱きはじめたのはそれ以前でしょう。いくつかの証言によって、その時期は1899年から1900年ごろに遡ることができます。しかし、それはたいして問題ではありません。彼女が入院させられたのは妄想をもっていたからではありませんでした。カミーユの奇妙な生活ぶりが目だったため入院措置がとられたのです。
そうした行動が、家族を含めた周囲の者に、彼女が妄想性精神疾患にかかっていることに気づかせたのです。おかしなことを言うだけでは、まわりの人間を警戒させませんが、反社会的な常識外れの行動をするのを見れば、精神病の存在に気づくのです。
本書のサブタイトルに挙げた「天才は鏡のごとく 一方の側は光を受けるが もう一方はざらざらと錆びついている」というフレーズは、ポール・クローデルが書いたものです。天才とは、内奥に狂気を孕みながら創作する存在だとすれば、その天才の光と影をこれほど言い当てた言葉はないでしょう。しかも、同じ気質をもちながら、自分は信仰によって破滅を免れむしろ「光」に生きたのに対し、狂気にからめ取られて「ざらざらと錆」ついた側を生きてしまった姉カミーユは、ポールにとって悲劇的分身でもありました。
カミーユの作品世界の際立った特色は、そのどれもが彼女自身の内面のドラマを表彰している点にあるでしょう。最初の傑作『シャクンタラー(1888)』では肉体の結合を通して到達される魂の融合と愛の神秘を、『ワルツ(1893)』では音楽のもたらす陶酔に身をゆだね、忘我の境地で旋回する男女の愛の恍惚を表現したカミーユですが、『分別盛り(1898)』では一転し、取りすがり哀願する若い女を置き去りにして、醜い老女のほうへと引きずられてゆく壮年期の男という男女三人の群像のうちに、ロダンをめぐる三角関係とその破綻のドラマをアレゴリックに造形化しています。
ロダンと決別してからのカミーユは、もう決して新たな愛の群像を構想することはありませんでした。「運命」を擬人化した『運命の女神(1900)』の、身体を弓形にそらし後方へ傾斜した非対称なポーズ、腰からまとった流れるようなドレープ、これはまさに『ワルツ』から男性パートナーが欠けた構図ですし、右手を傷口に、左手はだらりと垂れて、いまにも崩れそうな瀕死の姿をさらす女性は、『シャクンタラー』から愛する伴侶を取り去った像以外の何ものでもありません。
あるときは目くるめく愛の昂揚を歌い、あるときは成就せぬ愛の悲哀と別離の苦しさを嘆き、またあるときは孤独と傷心を訴える作品のなかの女たち、それはカミーユ自身の分身なのです。「いつも何か欠けているものがあり、それが私を苦しめるのです」と、彼女はロダンに根源的喪失感について語ったことがあります。誇り高く自立心に富んでいましたが、反面とても繊細で人一倍愛を必要としたカミーユ――彼女にとって、愛を失った欠落感はいかばかりであったでしょうか。そうしてついには狂気の暗い淵へと飲み込まれていったのです。
女性が芸術家になるのがまだきわめて困難だった時代に、カミーユは芸術を志しました。19世紀には大芸術(絵画・彫刻)と小芸術(装飾・工芸)の区別が歴然とあり、前者は芸術家、後者は職人の仕事とされていました。そして大芸術には天才が必要ですが、女性には天才はないと考えられていたのです。女性に許されたのは、良家の子女のお稽古ごととしての絵やピアノだけでした。そんな慣習の色濃く残る時代に、彼女は自立した芸術家を目指し、なおかつ愛においても対等を求めて激しく闘いました。
カミーユの作品がわたしたちを感動させるのは、それまでもっぱら男性によって見られ描かれる対象だった女性を、女性の目で見て、その真実を誰よりも鮮烈に表現したからでしょう。作品が生命感に満ち、精神的息吹に満たされているのは、自らの存在の内奥から霊感を汲み上げているからです。鶴女房が自分の羽を一本ずつ抜いて美しい織物を織ったように、カミーユは自分の命を削るように彫像をつくり、そこにその時々の感情と思索を、喜びと絶望を、つまり魂を刻み込んだのです。皮肉なことに、彼女の歓喜も苦悩も、すべてはロダンその人から由来してあったのですが――。
カミーユは長いこと忘却の底に沈んでいました。フランスで再評価の動きが起こったのは1980年代のこと。回顧展が開催され、伝記や研究書があいついで出版され、劇や映画が上演されました。日本にもブームは波及し、1987年に最初の展覧会が開催されました。
(2021年7月16日)
本の花束(6)ベッティーナ・ヒューリマン『子どもの本の世界/300年の歩み』(1968年、福音館書店)
「子どもの本」といえば童話や絵本が思い浮かびますが、わたしはまったくと言っていいほど、これらの本には触れたことがありません。わたしが子どもだったころ、二つ上の姉がキリスト教幼稚園に通っており、月ごとに聖書をもとにした絵本をもらってきました。その絵本も読んだはずですが、いっさい記憶にありません。
せいぜい思い出せるのは『ムーミン』です。それも絵本ではなく、テレビアニメで観ました。大人になるにつれて、作者のトーベ・ヤンソンはレズビアンだったとか、作者を投影しているのは“おしゃまさん”だとか、いろいろな情報が入ってきました。まずデザインが気に入っているので、お気に入りのマグカップが数個あります。
20代のころ、とある演劇パフォーマンスを友人と一緒に観たことがあります。登場するのは日本人だけではなく、外国人もたくさんいました。その外国人が「ヒャクマンカイシンダネコガイマシター!!」と何度も叫ぶのです。友人が「『100万回死んだ猫』だって。有名だもんね」と感心していました。わたしはさっそくその本を探しに行きました。本ではなく絵本だと、買い求めた書店で初めて知りました。その絵本はいまだに本棚に所蔵してあります。
ほかにも『はらぺこあおむし』とか『長くつ下のピッピ』とか、名前は知っていますが、まだ読んだことはありません。絵だけ知ってる絵本は『くまのプーさん』『星の王子さま』『ピーターラビット』があります。
そもそもわたしは、童話や絵本が苦手でした。クラスメイトたちはみな『赤毛のアン』『ロビンソンクルーソー』などの“児童文学”をどんどん読んでいます。それらの本は、わたしには興味がなく、手に取ることもしませんでした。
中学になって国語の教科書を読みますが、全然ピンときません。長い小説は読むと頭が痛くなります。しかたがないから図書室で詩集を借りました。詩は短いからすぐに読めます。いろんな詩人のいろんな詩集を読み漁りました。また、級友に教えてもらった漫画作品も「これが文学だ!」的なインパクトで読み続けています。
あるとき、わたしは気づきました。“児童文学”とは、大人向けの本を、大人が子供向けに換骨奪胎して差し向けた、人畜無害で保守的で道徳的な(つまり退屈な)文学ではないかと。倉橋由美子がこう言っています。「物語には“毒”がなくてはならない」。わたしもその通りだと思います。大人でも子どもでも、日々生活する空間時間のなかに、善だけではなく悪も存在しているはずです。善だけを見て悪を見ないふりをして生きることは、不都合な真実に向き合わずに生きることだと思います。“児童文学”とは一種の偽善である、とわたしは思います。
いま、わたしは、むしろ本がなくては生きていけません。ネットがなくても生きていけますが、本のない生活は想像を絶します。そのくらい本に依存しています。
前置きが長くなりました。実はこの本の前に、同著者の自伝『七つの屋根の下で――ある絵本作りの人生』を読みましたが、児童文学に疎いわたしにはさっぱりピンとこず、「児童文学研究者なら誰でも知っている」「大冊の見事な名著」「そのとてつもない博捜力と、みがきぬかれた感性と見識に支えられた本」「学者的な研究とはちがった文化を創造する市民的情熱と批判精神、いいかえれば、未来の市民である子どもたちのための子ども文化世界共和国づくりへの夢が、まるで感動的なまでに息づいて」いる本として紹介されていたこの本を紹介します。大著なので、紹介しきれるかどうか自信がありません。
ヨーロッパで最初に文字に書きとめられた民話は、おそらくジョヴァン・フランチェスカ・ストラバローラの「楽しい夜」(1550)であろう。この本で初めて、私たちになじみの深い民話のモチーフがでてくる。しかしイタリアの民話を最も豊富に載せているのは、ジャンバティスタ・バジーレの「お話のお話」である。これは最初ナポリの方言で書かれた。バジーレは1575年ごろ生まれ、幸運を求めてさすらい、イタリアのあちこちの宮廷にいろいろな資格でつかえた。バジーレは学者であり、詩人であり、ようするにすぐれた精神の持ち主であった。バジーレは(公頁)歌、牧歌およびあらゆる種類の宮廷詩を、当時の誇張した文体で書いた。バジーレはおおくのアカデミーに所属していたが、なかでも故郷ナポリでいちばんおおきい「なまけ者のアカデミー」の会員であった。そしてみずから「なまけ者(Pigro)」と名のった。しかしバジーレは、当時の宮廷ではめったにみられない、正義と誠実に対する感覚、およびナポリの庶民の欲求と自然な態度を理解する感覚を持ちあわせていた。それを表現しようとして、バジーレは民話を物語り、しかも故郷の方言で書いたのである。のちのグリムやペローと同じく、バジーレは女たちが子どもにしてやっている話を土台にしたが、それはもっぱら口から口へ伝えられてきた民話で、なかにはたいそう原始的なものもあった。この民話集が出版されたのはバジーレが死んでからあとのことで、1634から1636年にかけてであった。つまり、ペローの有名な民話集にゆうに60年先んじている。
ペローの民話もそうだが、バジーレの民話は、けっして民衆の口から聞き集めた、民俗学的な収集につきるものではない。あの活力にあふれるバロック時代の表現でもある。バロック時代はみごとな絵画となっていまもなお生きつづけている。太陽ののぼるのをみれば、あれは太陽が金のほうきで暁の空をはいているのだ、とかならずこれを擬人化して考えたのである。自然の描写は、それが比喩や象徴として用いられているときですら、個性的で力にあふれている。筋の運びは波乱に富み、ときには血なまぐさく、あるいは術策をめぐらすなど錯綜をきわめるが、かならず正義の勝利に終わる。不必要に飾りたてた細部の描写はあまりみられないが、一方、対話は機知と風刺にあふれ、気どったところはまるでない。この対話を借りてバジーレは、なによりもまず時代にむかって真実を述べているのである。
「なまけ者のアカデミー」に所属する、人間的でユーモア豊かなこの「なまけ者(ピグロ)」の話の聞き手は、聡明な人たち、つまり同じクラブの会員たちであったろう。しかしまたバジーレが、のちのペローやグリム兄弟と同じく、物語の骨組みを、町なかの女たちから仕入れたことは否定できない。バジーレが物語ったのは、断じて子どものための民話でなかった。確かにおおくの点で、この物語は、子どものための民話と結びついてはいるけれども……。なにしろここには、「灰かぶり」や「いばら姫」のような話がでてくるのだから、それは否定できない。しかしまた、近東との近いつながりをさし示しているものもある。とりわけ、不実な黒人女奴隷の枠物語がそうである。この女奴隷は最後に扉があらわれて、善良なしっかりした王女が当然の勝利を手に入れることになる。物語全体をまとめているこのかたい枠組みは、ペローにもグリムにもみあたらない。200年あまりをへだててヤーコブ・グリムは、バジーレと同じ血筋の兄弟と認めた。そしておくればせながら、バジーレの名声を北方の国々にひろめる手助けをした。ヤーコブ・グリムの序文をそえた最初のドイツ語訳は、1846年にあらわれた。
イタリア本国でも、ベネディット・クローチェがこの物語を、すばらしい標準イタリア語にうつしている。しかしクローチェはなにもこの本を単に大衆むきの民話集と思っていたわけではなく、「イタリアン・バロックの最もすばらしい本」とみなしていたのである。バジーレの民話集はのちの最も有名な二つの民話集と純粋性および新鮮さを共有しており、それは今日でも失われていない。機知とわき起こる民話的空想にかけては、バジーレの民話はくめどもつきない。そしてほかではめったにみかけない特異な民話の要素を含んでいる。なかでもいちばんすばらしいのはたぶん、海竜の心臓を煮ているうちに、その湯気にあたって、台所にあるものがなにもかも子をはらむ場面であろう。料理女ばかりでなく、道具や家具も子をはらみ、いすが小いすを、安楽いすが小安楽いすを、なべが小なべを産む。いのちない物にいのちをあたえるこういううまいやり方は、アンデルセンになってようやくまたでてくる。(「イタリアの民話」)
30年戦争によって心ならずもおおくの国々を流浪したコメニウスは、旅の途中で子どものみじめなさまをたくさん目にしたにちがいない。いまなら「見捨てられた子どもたち」というところであろう。当時の学校がどのような状態にあったかはよく知られている。コメニウスはまず最初に、学校制度の改革に力をつくした。そして、あらゆる階級の子どもに対する義務教育、とくに男の子も女の子も平等に受けられる義務教育を要請した。次にコメニウスは、実物に即した語学教育、身体の鍛錬、衛生学、手工をふくむ体系的なカリキュラムを組んだ。現代の教育学者にとっては、コメニウスは守り神のようなものであろう。なにしろすでに300年もまえに、今日その一部がようやく実現しつつあるようなことを求めていたのであるから。そして、コメニウスは革命的な教育学の本を書いた、「大教授学――またはすべての人にすべてのことを教える術」と「語学入門――または開かれた言語のとびら」である。いずれもはつらつとした授業をめざす本であった。
[…]
これまで、子どもとか人間教育の分野で仕事をした偉大な人物のうちただの一人も、子どものための本を作っていない。ルソーも書いていなければ、ベスタコッチも書いていない。フレーベルは母親用に子守歌を書いたが、いまは忘れられてしまっているし、また忘れられてもしかたのないようなものである。カンペはドイツの「ロビンソン」を書いたが、そのかわり教育者としては忘れられてしまっている。しかしコメニウスは、教育者、偉大な創始者として、いまなおけっして忘れられてはいない。「世界図絵」は、いわば当時の哲学の理念が民衆のために作りだしたものであるが、コメニウスはこの本を作ることによって、一つの発展にスタートの号砲を鳴らしたわけである。この発展は今日ようやくその頂点に達したかにみえるが、同時にまた袋小路におちいり、そこから抜けだすのはなかなか容易ではない。
題名までちょうだいした「世界図絵」の純然たる模倣の絵本がおおく出版されたが、時がたつにつれて、子どものためを思うおおくの努力が実を結び、たのしく教える絵本の洪水が、常に知識欲に燃えている子どものうえにどっと押しよせてきた。この洪水のなかから、二、三拾いだしてみることにしよう。それらの本はいまこそコレクションの宝物として大事に保存されているが、昔は行儀のよい子どもの日曜日のたのしい続き物であった。
これらの本でたいせつな点は、そのどれもが子どもにふさわしい宇宙全体の像を家庭に持ちこんだことである。この宇宙像はよく整理されたもので、啓蒙主義の理性が数十年にわたってそのささえとなった。この宇宙は、近いところ遠いところから事物や生物を寄せあつめたもので、超自然的な世界や人間の内部、骨格、魂の動きといったものまで含んでいた。これらの本はどれか一冊もてばすべて用がたりた。少年ゲーテには、ささやかなコメニウスの本で満足がいった。しかし次の世代の子どもになると、もうはるかにぜいたくなものを手にいれている。しかしその本は、豪華な作りとそれに応じたたたかい値段のために、「世界図絵」とはちがって、もはや庶民には手のとどかぬものとなっていた。
(「第三章 コメニウスから現代の絵本まで――または絵による教育」)
まだまだ引用がありますが、それを書くと長すぎるので、やめにしておきます。その代わり、目次を書いておきましょう。
第1章 子どもの魔法の角笛――童謡の今昔
第2章 むかしむかしあるとこに――民話とその由来についての覚書
第3章 コメニウスから現代の絵本まで――または絵による教育
第4章 ロビンソン――夢と教育の手段
第5章 「鹿殺し」から「げんこつ大将」へ――子どもとインディアンの関係、および子どもはインディアンのイメージをいかなる本からえてきたか
第6章 ハインリッヒ・ホフマン博士――「もじゃもじゃのペーター」など子どもの本の作者で、ライメリッヒ・キンダーリーブともよばれる人
第7章 醜いあひるの子――童話の詩人ハンス・クリスチャン・アンデルセン
第8章 あぶくの言葉――まんがの発達について、およびヴィルヘルム・ブッシュからウォルト・ディズニーにいたるまんがの功罪
第9章 一枚絵――どの年齢の子どもにもむくいちばん値段のやすい精神の糧
第10章 政治と子どもの本――児童図書の古典がおよぼした政治的影響。政治的傾向を持つ現代の子どもの本。全体主義国家における児童図書
第11章 ナンセンス――児童文学においてイギリスの特徴をもっともよく表している要素
第12章 空想と現実――ピーター・パンから長くつ下のピッピにいたるナンセンスな作品
第13章 ジャン・ド・ブリュノフ――世界の子どもにババール王様とセレスト、子猿のゼフィールをおくった人
第14章 宇宙からきた小さい王子――アントワーヌ・ド・サン・テクジュペリの「星の王子さま」という人物についての試論
第15章 写真――教育および子どもの本におけるあたらしい要素
第16章 20世紀の絵本
第17章 アメリカの子どもの本の特徴
第18章 スイスの子どもの本の歴史から
第19章 文学者が子どものために書けば
(2021年7月9日)
本の花束(5)広河ルティ『私のなかの「ユダヤ人」』(1982年、集英社)
第2回(1982年度)PLAYBOYドキュメント・ファイル大賞で最優秀作品受賞作となった本書の著者は、イスラエル生まれのフランス人で、1981年3月、フランス国籍を失いました。また同時に、日本における帰化申請は、法務省において「日本社会への同化の程度に疑問がもたれたためである」ことを理由に、許可しないことを決定しました。
私は日本人になるために法務省の指導によりフランス国籍を離脱したが、その直後に帰化は認められないと宣告されたのである。私は日本で、無国籍者になってしまった。
広河ルティはアムネスティの弁護士の助けで、「彼女は日本人の夫とともに11年以上日本に定住し、その間に日本国籍をもつ二人の子どもをもうけ、何ら日本人と変わらぬ家庭生活を維持している事情にてらし、不許可の理由はまったく説明的ではない」という、帰化不許可の具体的な理由開示の請求を行いましたが、それでもなお法務大臣および法務局長は、その理由を「明らかにすることはできない」との一点張りでした。
ここで問題となっている国籍法第4条では、帰化の条件を次のように規定している。
1)(帰化を申請するときまで)ひきつづいて5年以上、日本に住所を持っていること。
2)20歳以上で、本国法で(普通の人間としての)能力を有すること。
3)素行が善良であること。
4)自分ひとりの力で、暮らしをたてられる資産、または日本の国籍をとれば自動的に前の国籍を失うこと。
5)現に国籍を持っていないか、または日本のその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したことがないこと、またはそういう団体に加入したことがないこと。
これは「普通帰化」と呼ばれ、次の第5条は「特別帰化」といい、日本人女性を妻とする外国人や日本生まれの人に対してのものなので、条件は第4条よりゆるやかである。さらに日本人男性と結婚した外国人女性に対しては、第6条の「簡易帰化」が適用される。私の場合はこれに該当し、帰化はひじょうに楽なはずだった。
一方、無国籍者とは法的に存在しない人間のことなのだが、日本では、日本人でない者は「外国人」と規定されるので、無国籍者は「外国人」に含まれるとされる。しかしあらゆる国の庇護が受けられないため、基本的人権すら根底から否定される可能性を絶えずもっている。パスポートがないからどこにも行けず、免許もとれず、そして横浜にある収容所に隔離されることもあり、その人々は引き受け国が見つかるまで何年も収容所生活をしなくてはならない。
私の場合は特殊な例だが、日本はその歴史のなかで巨大な数の無国籍者を生み続けてきた。第二次世界大戦時、日本がサハリンに連行した4万3千人の朝鮮人のうち4千人余りは無国籍者になった。同じく200万人近くの強制連行された朝鮮人は、1952年に国籍を剥奪されることになった。法務省の通達によれば「朝鮮と台湾は(サンフランシスコ)条約発効の日以後、日本領土から分離されるので、朝鮮人、台湾人は日本本土在住者も含め、すべて国籍を喪失する」とある。在日朝鮮人のほか、沖縄の無国籍児の問題も拡大しています。米兵と日本人女性の間に生まれた子と、その子が成人して結婚してできる子どもで、無国籍者は、現在100人ぐらいと見積もられているが、ここ何年かのうちに数千人になるとみられている。それはアメリカ国籍をとっている子どもたちが、成人して日本人と結婚して子ができるときに同じ問題を抱えることになるためである。
これらの問題の多くは、日本が父系優先血統主義をとっているからである。しかし、ヨーロッパとても父母平等の血統主義に変更したのは、そう古いことではない。フランスで1973年、ドイツで1974年である。そして日本でも法改正が問題になっている。
生まれも育ちも日本であり日本語を話すわたしは「日本国籍を持つ日本人」ですが、彼女のように疑問も不都合もなく、それについてわざわざ調べることもなかったので、日本国籍を持つのはなんて困難だろう、と初めて思いました。不勉強にもほどがありました。
イスラエル生まれのユダヤ人である彼女は、フランス領事から「ユダヤ人はすべてのイスラエル人でもあるわけですから」と言われ、法務省の課長からも「イスラエルの帰還法は、世界中のユダヤ人にイスラエル国籍を持つ権利を与えています」と言われました。つまり、「イスラエルは世界中のユダヤ人がイスラエルに移住することを望んでいる」と。
結局、彼女が日本に帰化できないのは、彼女がイスラエル生まれのユダヤ人だからです。それでも彼女はイスラエル国籍を取らず、無国籍者となりました。と同時に「ユダヤ人とは何か?」という疑問が起こり、アイデンティティ探求の作業として、ポーランド生まれの両親にさまざまな質問をしましたが、彼女は両親や兄姉と、そもそも何語を使って話していたのだろうか、と躊躇しました。まず、<あとがき>で彼女はこう書いています。
[…]私は日本に12年以上住んでいるが、美しくまちがいのない日本語を使いこなせるわけではない。[…]オリジナルな原稿は三つの方法で用意した。三分の一はフランス語で私が書き、私の友人が日本語に翻訳した。イーディッシュ語の手紙や文章は、私がフランス語に訳して、次に日本語にした。次の三分の一は、私がテープに、ヘブライ語と英語のちゃんぽんで吹き込んだものを、隆一が日本語に訳した。残りの三分の一は、私自身が日本語で書いたものである。[…]
父や母が夢の中に登場すると、私はイーディッシュ語を使っていた。兄や姉の場合はフランス語、イスラエルに住む親戚とはヘブライ語、子供たちや義母とは日本語という具合だ。ただ私の結婚相手と話す場合だけは、少し事情が違った。日本語とヘブライ語のミックスなのだ。
それから十年以上たち、現在私はフランス語会話の教師をしているが、授業以外では日本語しか話さないようになった。食事はいつも箸を使い、タタミの上に布団を敷いて寝る。冬は大抵コタツに入っているし、夏には下駄を愛用している。私の友人はほとんどすべてが日本人だし、私も日本人一般と同じように、夏の湿気に悩まされ、秋のモミジを美しいと思い、乾燥して寒いが陽光には恵まれた冬を素晴らしいと思っている。春の桜の季節は、いつもうっとりしている。
およそ「権威」なるものに対する日本人の卑屈さは、どうも評価できないが、日本人の持つ素朴さと善良さとは、私にとって新しい発見で、それらを私は愛した。日本はあらゆる意味で、私の肌になじみ、空気のように自然になった。
日本に同化するというとは、このようなことではないだろうか。同化するにつれ、私には日本の中のさまざまな「ユダヤ人問題」が見えてきた。それらは被差別部落問題、在日朝鮮人問題、アイヌ問題であり、一人の女としてはこの国の高度に完成された父権社会、母親としては、この国の息詰まるような教育の問題である。それらが一切見えなくなるぐらいにならないと、同化したとは言えないというのだろうか。
[…]
一方で、私の心の底流に「同化」への不信感が存在し続けたことも事実である。「同化」という言葉には、何かしら欺瞞の臭いが漂っていた。本質的なところで、もとの状態が含んでいる矛盾からの逃避という後ろめたさがあった。それは決して、私に日本に解けこむのを止めろとか、ユダヤ人の運命共同体の一員として復帰せよとかいうことではない。私は心のどこかでユダヤ問題にこだわり続けており、そしていまだに世界からユダヤ問題が無くなったわけでもなく、かといってイスラエルも、同化も、この問題の解決ではないと思い続けていたのである。
[…]
「しかし、虐待され、殺害された人々と無条件に結びついているという点では、私はユダヤ人である。私はユダヤ人の悲劇は私の悲劇であると感じている。その点で私はユダヤ人である」(アイザック・ドイッチャー『非ユダヤ人的ユダヤ人』岩波新書、鈴木一郎訳)
両親がポーランドを出てゲットー(強制収容所)に入り、ナチスの手を逃れてイスラエルに移民した経験は、彼らにとっては思い出したくもない苦痛の記憶、ナチスの虐殺という歴史的体験でした。それで彼女は「知る限りの世界中のユダヤ人」「各地のホロコースト研究所、平和主義者、ジャーナリスト、昔の友人たち」「イスラエルのキブツ(集団農場)」に手紙を送りました。
そもそもわたしは「誰が、なぜ、どのようにしてイスラエル政府を誕生させたのか?」が薄々とではありますが、ずっと疑問でした。世界史の教科書は多くを語らず、専門書はわたしにとってハードルが高すぎます。ナチスやホロコーストの映画(ドキュメンタリーやドラマなど)をたくさん観ましたが、彼女の両親が生きた道は新鮮でした。「ユダヤ人の地下活動家の決死の覚悟で、アウシュビッツやヘルムノの大量虐殺のニュースが伝わるのは1942年夏のことである」「ワルシャワ・ゲットーは最後の武装抵抗をした。ZKK(ユダヤ調整委員会)とZOB(ユダヤ戦闘組織)がこの任に当たった」。
そして、1949年4月21日、彼女が三つ子として生まれたのも、両親は「単なる偶然」とは考えず、「生き延びられたこと」「イスラエルの誕生」「三つ子の妊娠(その直前の5月14日)」を「神の啓示」だと感じ、イスラエル移住を決意したのです。
当時私の両親だけでなく、世界中のユダヤ人をシオニストの側に押しやる強力な状況が存在していた。ユダヤ難民の引き受けをしぶり、ユダヤ人問題を自国内で解決せずにアラブの国に押しつけたヨーロッパ諸国、そして石油産出地帯に打ち込んだ楔としてイスラエル国家を位置づけようとした帝国主義的野心を持つ大国、最後に解放の具体的プロセスを提出することに失敗し、ホロコーストを経たあとのユダヤ人の状況の変化を把握しきれなかった社会主義者たちとスターリンのソ連、すべてがユダヤ人をシオニズムの方向に向けようとした。
「アウシュビッツは新興ユダヤ民族意識とその国家イスラエルの恐るべき発生の地であった。……600万のユダヤ人の灰の中から『ユダヤ社会』という不死鳥がとびたっていったのである。何という『よみがえり』であろう」(ドイッチャー『非ユダヤ人的ユダヤ人』)
戦前のユダヤ社会で模索されていた「ユダヤ人問題解決の三つの方法」、つまり同化、社会主義、シオニズムのうち、600万人の虐殺を経て生き残ったのは、ドイッチャーが敗北感とともに回顧しているように、シオニズム、つまりパレスチナにユダヤ人の国家を作ることだけだったのである。同化という方法は、不信感をもって迎えられた。ヒトラーが同化ユダヤ人も虐殺してしまったからである。さらに社会主義による解決法も説得力を失っていた。ファシズムの意図を見抜けず、対処する方法も立てられなかったからである。そして狂暴なナチスの荒れ狂った後の瓦礫の中に悄然と立ちすくむユダヤ難民を、ビザもパスポートもなしで、国家ぐるみの保障で受け入れる国家が必要だというシオニストの説明は、説得力をもって迎えられたのである。
このような状況下でシオニストに変身した私の両親は、お腹の中の三つ子を持参金として、イスラエルに嫁いできた。1949年のはじめのことである。当時のイスラエルは、国連分割決議によってユダヤ国家と決められた地域ばかりでなく、パレスチナ国家に決められた地域からも武力で住民を排除し終わり、そのために生じたパレスチナ難民の受け入れを拒絶し、残された家屋を世界中のユダヤ移民で埋めようと働きかけ、同時に内に向かっては、産めよ殖やせよというキャンペーンを繰り広げていた。このような時代のイスラエルで初めての三つ子の誕生は、センセーショナルな事件となり、私たちはベングリオン首相の祝電を受け、祝い金まで贈られたのである。
私たちは歴史の申し子として誕生した。もしヒトラーがいなければ、私はポーランド人として誕生していただろう。両親がサマルカンドに留まっていたら、私はソ連人として生まれ、もし三つ子でなければフランス人として生まれたかもしれない。
[…]
私はイスラエルと一歳違いの姉妹だった。私は最初この姉の存在に当惑し、そのあと彼女に親しみを覚え、そして憎むようになり、今では彼女が不正な存在であると考えている。
夏 雨が降る
冬 雪が降る
そして 呪われた長い道を
私は ひとりさまよう
私があれほど愛したすべては
死に絶え
呪われた力に殺され
そして あれほどの苦しみのあと
あれほどの恐怖のあと
結局 私はポーランドを去らねばならない
(『ゲットーの子守歌』より 松井真知子訳)
この本は、著者のさまざまな感動と衝撃にみちたエピソードの数々によるイスラエルからの離脱の話と同時に、いわばアンチ・セミティズム(反ユダヤ主義)と同じコインの裏表にあるシオニズムの非正当性に光をあてる作業が語られています。その作業にみられる彼女のねばり強さと徹底性は、まさに驚嘆に値します。わたしたちはその著者の追究の展開から、瞠目すべき多くのことを知るでしょう。
(2021年7月2日)
本の花束(4)大田洋子『屍の街・半人間』(1995年、講談社文芸文庫)
原爆をテーマにした物語は、こうの史代『この世界の片隅に(2011)』が出版され、同年にテレビドラマ化され、2016年には劇場アニメとして公開されました。わたしも劇場に足を運びました。作品はひじょうに素晴らしいのですが、一部の「感傷的(ノスタルジーかつセンチメンタル)」な観客もあり、残酷で悲惨な原爆という記憶を「ふるきよき思い出」として「美化」している、との批判がありました。
「原爆」といえば、わたしの世代では、小学校の図書館に中沢啓治『はだしのゲン』がありました。わたしは全部読んだはずですが、つねに漫画がクラスのなかにあるものですから「いつでも読める」と思い、途中で飽きてしまって、新しい別の漫画に関心が移るのでした。
8月になると毎度のように「終戦(本当は“敗戦”ですが)記念日」の式典がテレビで放映されます。井上ひさし曰く「なにを言われようと、堂々と大マンネリズムの道を歩いて、毎年8月には、私たちは<ヒロシマ・ナガサキ>のことを語らなければならないのだ」。
「戦争を知らない子どもたち」であるわたしたちは、ヒロシマ・ナガサキに原爆を投下された体験がなく、「世界で唯一の被爆国」でありながら、その自覚はありません。8月になると<いつものアレがくる>と思い、うんざりし、<大マンネリズム>になるのもしかたがありません。
敗戦後のもっとも早い時期の文学者の発言に、1945年8月30日の『朝日新聞』に載った大田洋子の『海底のやうな光――原子爆弾の空襲に遭って』という文章があります。大田の文章は、ほかならぬ原爆の問題をとりあげての文学者の最初の発言になっている、という点でも核時代のはじまりと日本文学との関係に正確に対応しています。
8月30日という日は、占領支配にあたる連合軍最高司令官マッカーサーが厚木に到着した日で、つまり米軍による検閲はまだはじまっていなかったから、大田はこの文章の中で被爆の時のすさまじい様子を、経験した通りに書き、それはそのまま発表されました。この少しあと、米軍は原爆被害に関する一切の報道を禁止するようになって、検閲はやかましくなり、1946年はじめに『近代文学』誌にとどけられた原民喜『夏の花』の原稿は、米軍の事前検閲で発表を封じられ、また、45年11月には完成していた『屍の街』も、48年11月になって『無欲顔貌』の章のほか重要な部分の若干を削ってようやく刊行されたくらいでした。
大田洋子、原民喜のほかにも、ヒロシマに執着した現代作家として井伏鱒二、堀田前衛、大江健三郎、阿川弘之、いいだ・もも、小田実らがおり、詩人としては栗原貞子や峠三吉がいます。ほかに劇作家たち、シナリオライターたちもいます。また、ナガサキについては、作家としては林京子、佐多稲子、井上光晴らがいます。
大田洋子(1903~63)は、広島で被爆した、戦前から活躍した作家でした。彼女の『屍の街』は、原爆の犯罪性を糾弾した世界で最初の克明で鮮烈な記憶であり、原爆文学の記念碑的作品です。それは、1945年の8月~11月にかけて執筆されたのでした。
私は『屍の街』を書くことを急いだ。人々のあとから私も死ななければならないとすれば、書くことも急がなければならなかった。
当日(8月6日)、持物の一切を広島の大火災の中に失った私は、田舎へはいってからも、ペンや原稿用紙はおろか、一枚の紙も一本の鉛筆も持っていなかった。当時はそれらのものを売る一軒の店もなかった。奇寓先の家や、村の知人に障子からはがした、茶色に煤けた障子紙や、ちり紙や、二三本の鉛筆などをもらい、背後に死の影を負ったまま、書いておくことの責任を果してから、死にたいと思った。
その場合私は『屍の街』を小説的作品として時間を持たなかった。その日の広島市街の現実を、肉体と精神をもってじかに体験した多くの人々に、話をきいたり、種々なことを調べたりした上、上手な小説的構成の下に、一目瞭然と巧妙に描きあげるという風な、そのような時間も気持ちの余裕もなかった。
私の書き易い形態と体力をもって、死ぬまでには書き終わらなくてはならないと、ひたすら私はそれをいそいだ。
広島に原爆が投下されたとき、一瞬の閃光のあと、激しい爆風が襲います。広島の街は瞬時にして焼け野原になり、焼けただれた死者が累々とあらわれます。まだ死んでいない被爆者たちも、大怪我や大火傷を負いながら、いずれ死んでいきます。「被爆したわたしもいつか死ぬかもしれない」と主人公はおそれ、「原子爆弾症という恐怖にみちた病的現象」を描いています。
死体はみんな病院の方へ顔を向け、仰向いたりうつ伏せしたりしていた。眼も口も腫れつぶれ、醜い大きなゴム人形のようであった。私は涙をふり落しながら、その人々の形を心に書きとめた。
「お姉さんはよくごらんになれるわね。私は立ちどまって死骸を見たりできませんわ」
妹は私をとがめる様子であった。私は答えた。
「人間の眼と作家の眼とふたつの眼で見ているの」
「書けますか、こんなこと」
「いつかは書かなくはならないね。これを見た作家の責任だもの」
大田洋子は、ウラニュームの放射線を浴びて“左の耳の中から下にかけて谷のように切られていた(『屍の街』)”というのに、そのとき蒲団のなかで寝ていたためか、一般的な原爆症になることからは免れました。その意味では、彼女は原爆症患者ではないということが、しばらくして判明しました。
しかし、それでめでたしということにならなかったのは、あるいはいつの日にか自分も、という疑いを避けられずにいたことと、現に周りの人びとをはじめとして多くのひとが原爆症を発病して死んでいくこと、いまなお戦争の火種はいつもどこかで燃えていること、等は彼女の心を深いところから傷つけてやまず、“原子爆弾から受けた心理の損傷(『半人間』)”はひどくなりました。
「混沌と悪夢にとじこめられているような日々が、開けては暮れる」
「西の家でも東の家でも、葬式の準備をしている」
「死は私にもいつくるか知れない」
『半人間』とは、つまり「廃人」のことです。生きているには生きているのですが、心は死んでいます。心のなかはいつも死の恐怖のことばかり考えているのですから。
広島市が一瞬の間にかき消え燃えただれて無に落ちた時から、私は好戦的になった。かならずしも好きではなかった戦争を、6日のあの日から、どうしても続けなくてはならないと思った。やめてはならぬと思った。…社会不安が全部ではなかった。そこからのがれる道のない、おのれの所属する国家への不信、世界への不信、人間への不信、自分の肉体と精神のぶつかる接触体への不信が、あたまのなかを暗くしている。この不信は自己への不信を裏書きするものであった。…またかと篤子は思った。現在そこにはないものの匂い、かつて体験したさまざまな臭気が、ときどきむかっぽく鼻さきを通りすぎる。最初にきた幻臭は、死体の腐臭であった。夏の日、大量な人間の殺傷によって経験された匂いだった。まる七年前に起きたことと、未来への不安な感覚は、日と時間の多少の駆引きにかかわりなく、篤子の心のなかに密着しているものだった。
本書の解説に小田切英雄が書いています。
同じ五四年の秋から『群像』連載がはじまる『夕凪の街と人と』では、“半人間”というデッド・エンドからとにかくぬけ出して、広島相生通りの原爆スラムや基町(もとまち)の戦災者住宅やの人びとの苦渋を描くことに転ずるが、この作家がとにかく『半人間』の制作でひとつのデッド・エンドにおける人間のあるがままの姿の強烈な表現として、それは記憶されざるをえない。
死んだ人間は、まず匂いが強烈だ、といいます。推理物のドラマでも、放置された遺体が発見され、我慢できずに刑事が吐くシーンがあります。ときとしてそれは、「卵か魚が腐ったような、タマネギが腐ったような臭い」と形容されます。『屍の街』で篤子がさまよった街で嗅いだのは、死体の腐臭である“幻臭”でした。
私は最近、長崎の原爆詩人福田須磨子の必読の無比の書『われなお生きてあり』(筑摩書房刊)が入手困難になっていることを知り、驚愕しました。私たちは、大田洋子や福田須磨子のような人を、二度死なせてはならないのです。彼女たちを忘却することは、まさしく犯罪といわなければなりません。
ヒロシマ・ナガサキとつづいて、次はオキナワ、そしてフクシマ、コロナウイルスによる世界レベルでのパンデミックがきます。過去のことではありません。歴史は地続きに現在まできています。マスコミの表層的な報道に流されずに、また「すべての報道は“娯楽”」だと思わずに、ほんのわずかに引っかかることがあれば、自分で疑い、自分で考え、自分で調べてください。「大文字の歴史」にごまかされないでください。
(2021年6月12日)