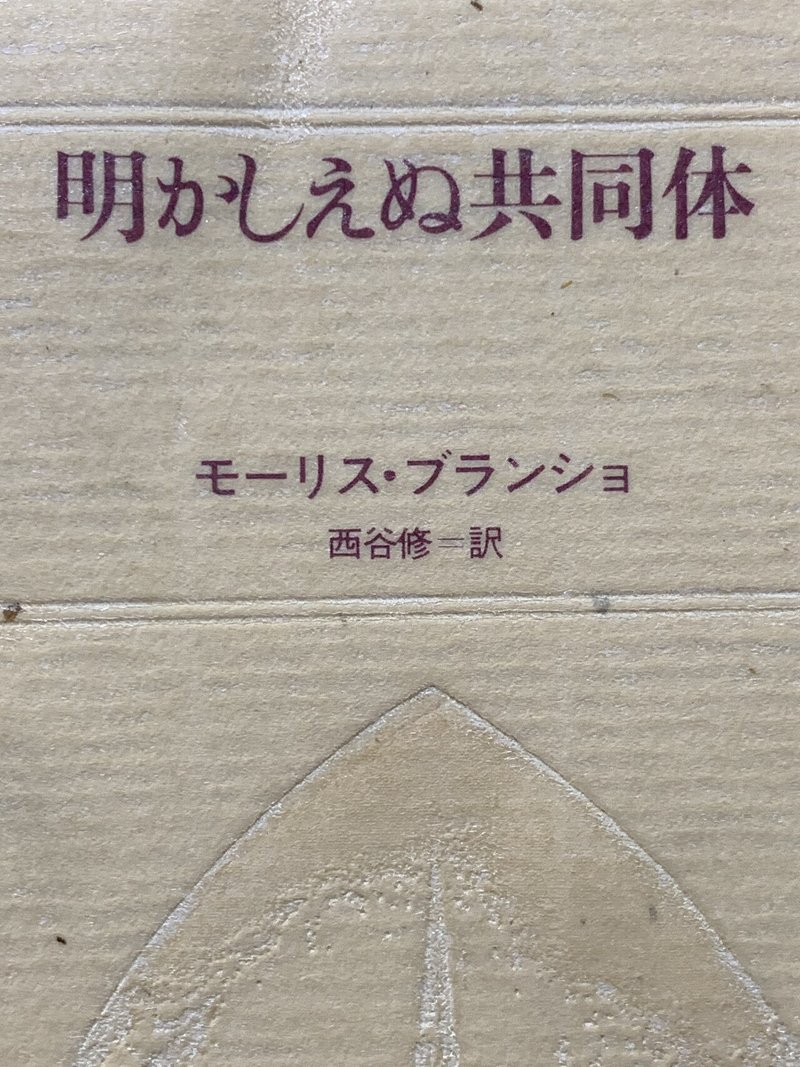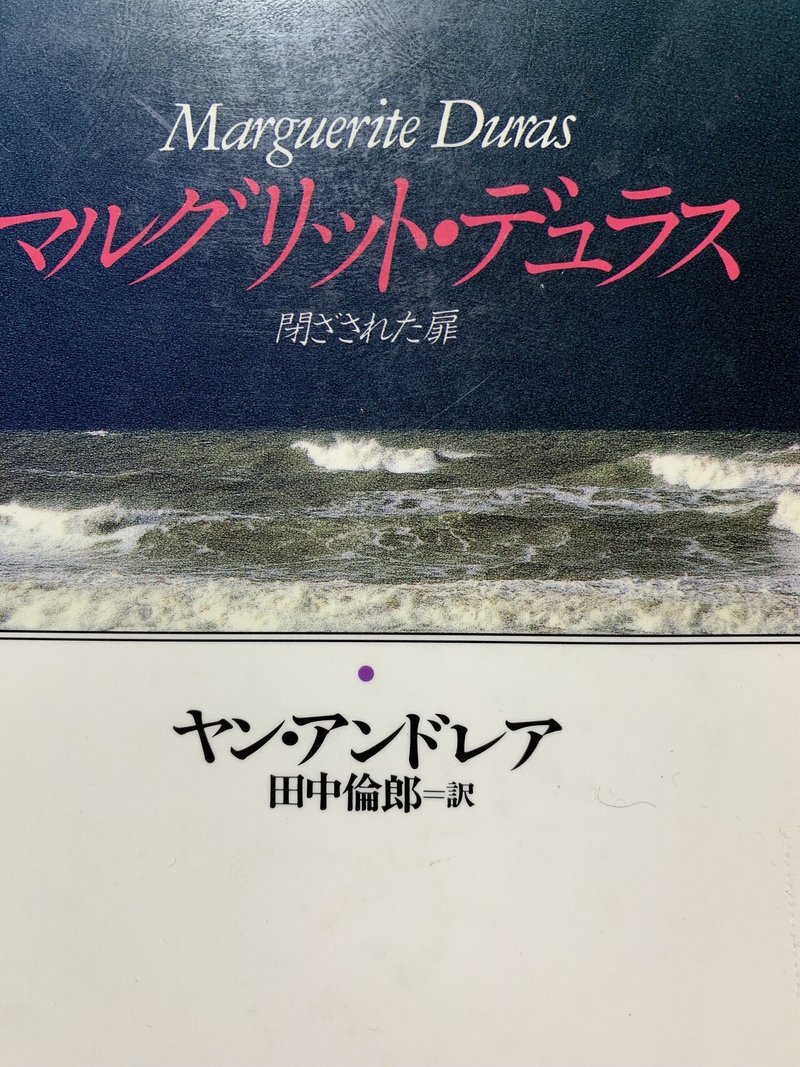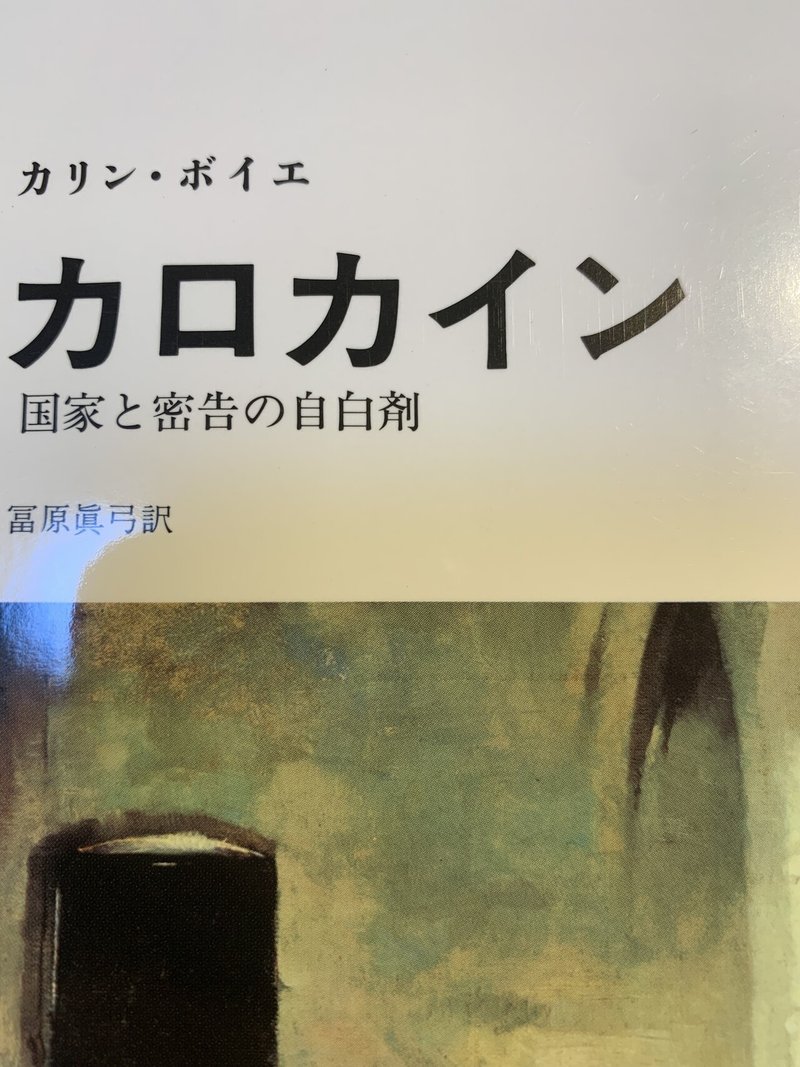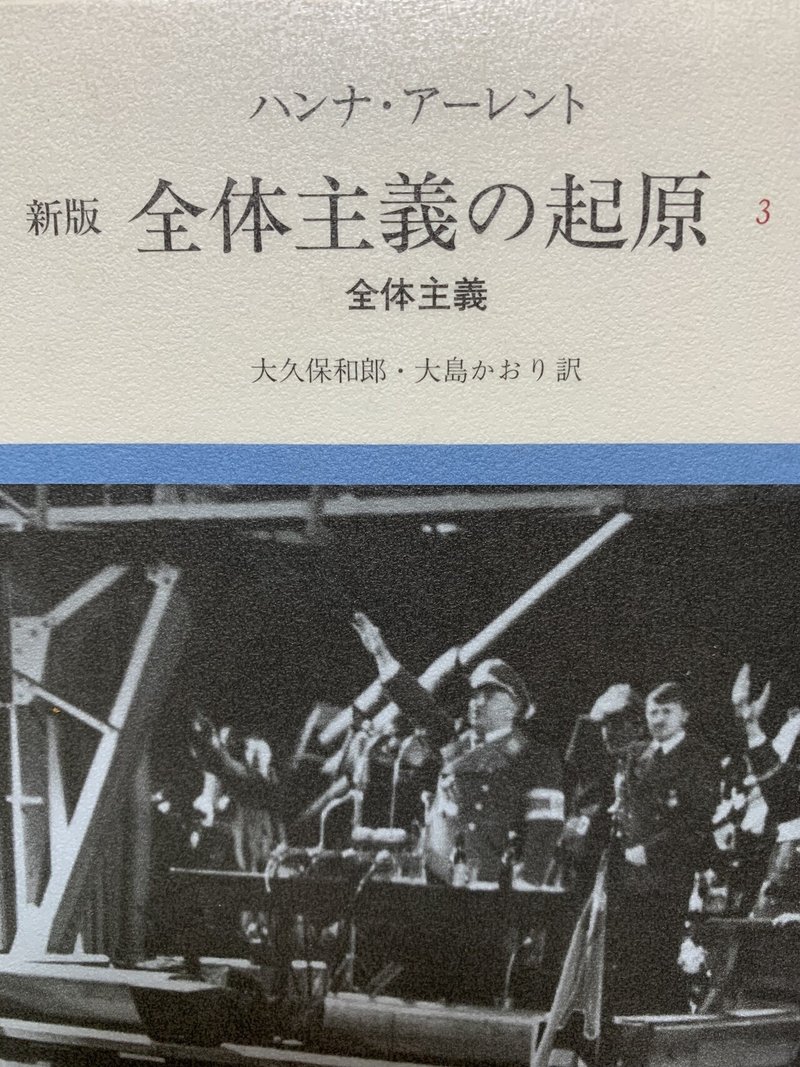マルグリット・デュラスからジョルジュ・バタイユ、そしてモーリス・ブランショ『明かしえぬ共同体』(朝日出版社、1984年)について
まだ全体の4分の1までしか読んでいないにもかかわらず、わたしはこの本の言いたいことがわかるような気がしたので、覚書のように書いてみます。あらかじめ断っておきますが、このテーマについて、何度も何度も書き直し反復します。
マイノリティとマジョリティの関係について、よくこう言われます。「マイノリティの心理を理解するために言葉でいちいち説明しなくちゃいけないが、マジョリティの心理は誰でも知っているしツーといえばカーであるから、説明しなくても理解できる」ゆえに「異性愛者は、なぜ異性を愛するのか? という問いに答えることはできない」と。
たとえば、同性愛だったり、ポリアモリーだったりします。最近、LGBT理解増進法の法案が提出されましたが、宗教右派のせいで法案が潰されました。アメリカもそうらしいです。同性婚は認められていますが、キリスト教右派が相変わらず「同性愛は病気」だと繰り返し主張しています。なかなか理解されません。
地球のほぼ概ねは異性愛者が占拠しているから異性愛文化が蔓延し、その代わり非異性愛文化が隅っこに押しやられています。
わたしがいま読んでるのは『共同体について』です。みんなわかっているでしょうけど、わたしはいま単独でいることが重要なんだ、ってことです。
非常に乱暴に表現すれば、「お互い愛し合ってるから一緒にいるとかアホみたいだぜ、どうせ死ぬときは別々だしな!」
1965年のジョージ・タウン、ガイアナ(人民寺院)の集団自殺も、宗教的な悟りをひらくために、なぜ集団でいないとダメなのでしょうか(かれらはおそらく発展しすぎてコントロールできずに限界を感じ、行き詰まっていたのです)? 仏陀はずっとシングルでいたのに? 元に戻りましょう! 自然に帰れ!
わたしが解説する前に原文を長々と引用します。長すぎるので途中で飽きても知りませんからね。
他でもないジョルジュ・バタイユの場合であり、十余年にわたって、現実、思考の両面で、共同体への要請を実現すべく試みた果てに、彼は孤独にとり残されたにみえるが、それは単なる孤独に立ち戻ったということではなく(いずれにせよ孤独ではあるが、分かち合われた孤独である)、共同体の不在へと転化しうる不在の共同体[不在を共有する共同体]に身をさらしていたのである。「完全に常軌を逸すること(限界の不在への自己放棄)」が、共同体の不在の規則である、あるいはまた、「私の共同体の不在に所属しないことが、誰にでも許されているというわけではない」(ともに雑誌「いっさいの待機に抗して」からの引用)。ここで、少なくとも「私の」という所有形容詞がもちこんでいる逆説に注意しておこう。私の死は、つねに私のものである我有化の可能性を崩壊させてしまうばかりではなく、誰に対してであれ帰属する関係のいっさいを崩壊させずにはおかないものではあるが、その私の死がそれでも執拗に私のものであり続ける。そのようなかたちで「私のもの」だというのでなかったら、共同体の不在がいかにして私のものでありうるだろうか。
ジャン・リュック・ナンシーは、バタイユが「現代の共同体の運命に関する決定的な体験を、おそらく最も遠くまで辿った人物である」ことを示しているが、私は彼の研究をここで繰り返してみようと思わない。あらゆる反復は、思考の道筋を単純化することでその力を弱めもするだろうし、テクストの引用はその道筋に手を加え、さらにそれを逆転しさえしかねないのである。とはいえ次のようなことを見失ってはならない。すなわちバタイユはつねに彼自身であり続けながら、絶えず自分とは別の者であろうとし、また歴史のもたらす諸変化や反復されることを望まないもろもろの体験の枯渇に応じて、容易に統合するすべのないさまざまな要請を絶えず展開してきたが、彼にはそれを強いた変貌の必然性、あるいは自身にたいする不誠実というものを私たちもまたわが身に引き受けるのでなかったら、このような思考に忠実であることはできないだろうということである。共同体について『呪われた部分』や、さらに後年の『エロティシズム』(これはある種のコミュニケーションの形態を特権化している)などの著作が、ほとんど同じ主題群を延長しており、これらの主題群を二次的なものとみなすことはできないが(そのほかに『至高性』に関する未完のテキスト、『宗教の理論』に関する未完のテキストをあげることができよう)、(おおよそ)1930年から1940年にかけて、「共同体」という言葉が彼の探究のなかでそれに続く時期以上に重きを占めていたということは確実である。政治的要請はつねに彼の思考形態をとって表れている。『有罪者』の冒頭はそのことを直截に物語るものである。戦争の重圧の下で書くこと、それは戦争について書くことではなく、戦争の地平のなかで、それがあたかも床を分かち合う伴侶でもあるようにして(戦争がひとにわずかな場所を、自由の余地を残すものとして)書くことなのである。
バタイユに代わって、なぜ「共同体」なのか、という問いをもう一度繰り返してみよう。答えはかなり明確に与えられている、「おのおの存在者の根底には、不充足の原理がある」(不完全性の原理)と。これが原理であるという点によく注意しよう。原理である、とはすなわちそれがひとりの存在者の可能性を統御し秩序づけるものだということである。従って、この原理としての欠如は補完の必要性を伴わない。存在者は、おのれ自身で満ち足りてはいないが、だからといってひとつの欠けることなき実質を形づくるために他の存在者と結びつこうとするのではない。不充足の意識は存在者が自分自身を疑問に付すことから生じる。そしてこの付議が果たされるために他者が、あるいはもうひとりの存在者が必要なのである。存在者は、単独ではおのれのうちに閉じこもり、眠り込み、そこに安らいでいる。あるいはこういってもいいだろう、存在者は単独(ひとり)ではあるが、自分が単独であることを知るのは、かれが単独ではないその限りにおいてである、と。「おのおのの存在者の実質は、他の存在者のおのおのによって絶えず異議提起を受けている」「私の考えは、私ひとりで考えたものではない」。ここには性質の異なるさまざまなモチーフが錯綜しており、それはそれで分析の対象ともなるだろうが、この錯綜は入り乱れたもろもろの差異の結びつきのなかにそれ自身の力を汲んでいる。あたかも数多の思考が小さな開き戸に殺到し、夥しいその数のためにかえってそこを通過できなくなっているかのようだが、それらの思考はすべてまとめてでなければ思考しえないようなものである。
ここで私たちは、容易に手なづけることができない難題に逢着する。共同体は、それが多人数であれ少人数であれ、(とはいえ理論的に言っても歴史的にみても、共同体は少人数のものに限られている――修道僧たちの共同体、ハシディズムの共同体、(そしてキブツ)、研究者たちの共同体、「共同体」を目指す共同体、あるいはまた、恋人たちの共同体)、ある合一への傾向、さらにはある縫合状態、つまりは集団的沸騰状態へと向かう傾向をもっているように思われる。だがそうしたものが諸要素を糾合するのは、ただもっぱらあるひとつの一体性、単位(超個人性)をつくり出すためであり、そうなればまたそれは、自己の内在性に閉じ籠る単独の個人を想定する場合と同様の反論にさらされることにならざるをえないだろう。
共同体は、合一(それはいうまでもなく聖体拝領の全体によって象徴されるものだ)に通じうるということを、多種多様な例が示している。ガイアナの凄惨な集団自殺によって例証された、幻惑的力の支配下にあるグループ、『弁証法的理性批判』のなかでサルトルによって分析され名づけられた、融合状態にあるグループ(集列(数としての個人)と融合――運動中のある全体のなかで自己を滅却する、あるいは昂揚する、そのことによってしか自由でありえないという自由の意識――というふうに社会性のふたつの形態を対置する、そして軍隊あるいはファシストのグループ、ここではグループの各成員は、おのれの自由ばかりか良心をもグループを体現する一人の統領に預けるが、この頭(かしら)は定義上あらゆる侵害の彼方にあり、断ち切れるべくさし出されることがない。
その名が、彼に疎遠な読者の多くにとっては、恍惚の神秘神学、あるいは恍惚体験の世俗的探求を意味するものと受け取られているジョルジュ・バタイユが、「何らかの集合的位格における融合の実現」(ジャン・リュック・ナンシー)を排除している(いくらかの曖昧な文章を除いては)ということはきわめて印象深いことである。彼はそれに深い嫌悪さえ抱いている。彼にとって重要だったのは、すべてを(自己自身をも)忘れ去る忘我の状態であるよりも、不充足でありながらその不充足性を断念できない現存が、活を入れられおのれの外に投げ出される、まさにそのことを通して貫かれる困難な歩み、超越の通常の諸形態をも内在性をもひとしく崩壊させてしまうこの運動(この問題については『終わりなき対話』に発表したテキストを参照されたい)のほうだったということは肝に銘じておかねばならない。
したがって(あまりにも性急な「したがって」ではあるが、それは承知のうえだ)、共同体とは忘我の境に達すべきものでもなければ、その成員は高められた一体性のうちに解消すべきものでもなく、そもそもこのような一体性は、共同体が共同体としての自己を無化すると同時に、それ自体も抹消されてしまうようなものである。とはいえ共同体は、たんにそれがおのれに課す限界のなかで、複数で存在するという意志を分かち合い、それを共有するというだけのものでもない。たとえそれが何もしないため、いいかえれば、共有されるべき分け前とみなされる可能性をつねにすでに免れていると思われる「何ものか」、つまりことばと沈黙とを共有するという以外にも何もしないためであるとしても。
ジョルジュ・バタイユが、「いっさいの存在者の基礎」として不充足の原理をもち出すとき、私たちは頭でなら彼の言うことを容易に理解できるように思う。しかし、それを納得するのは難しい。何に対して不十分なのか、生き永らえてゆくためには充分でないというのか。もちろん問題はそういうことではない。利己的なあるいは気前のよい相互扶助は動物社会にも見られるもので、単純な群居的共存の基盤とみなすにも充分ではない。群居生活は、おそらく階層化されてはいるだろうが、誰彼に対するこの従属関係のうちにも、決して特異化したことのない均一性が残っている。不充足とは、充足のモデルをもとにして結論されるものではない。不充足は、それに終わりをもたらすものを求めているのではなく、むしろ満たされるにつれてますます募ってゆく欠如の過剰をこそ求めている。おそらくこの不充足性が異議提起を呼び求めるのである。(モーリス・ブランショ『明かしえぬ共同体』)
これは推測にすぎませんし、まだまだ説明が足りないのも重々承知なのですが、わたしはこの「共同体」に「経済」をからめたいと思います。単身者よりカップルのほうが金がかかるし、ファミリーだとなお金がかかります。一方で、細々と個人で経営するより、1000人単位の大企業のほうが効率がよくて儲かるからです。
また、個人で考えてつくる詩や小説よりも、ドラマや映画のようにチームワークでつくるほうが自分の考えが広がるし(それを「錯覚」「勘違い」と言います)、結局そのほうが儲かるからです。
結局、お金やないかーい!
でも死んだらお金は天国(あるいは地獄)に持っていけないよ? 頭大丈夫?
(2021年11月28日)
ヤン・アンドレア『マルグリット・デュラス 閉ざされた扉(河出書房新社、1993年)』
作家で映画監督のマルグリット・デュラス(1914~1996)は、結婚して出産後の29歳のとき『あつかましき人々』を発表し、82歳で死去するまで、小説やエッセイを含む著作は20冊以上、映画は15本以上製作しています。本人も言っていますが、まさに「病的」です。中島梓のようなワーカホリックとは違います。「書かざるを得ない」のです。
かの有名な『愛人/ラマン(1984)』という映画も小説(ゴングール賞受賞)も、わたしはずっと避けてきました。なぜだかわかりません。ところが、今年(2021)になってようやく読みました。あらすじを言うと、主人公の末娘「わたし」は、幼くして父を亡くし、狂気に取り憑かれた母、横暴な上の兄、早逝した下の兄とともに貧困のなかで生活し、一方で、金持ちの年上の中国人の愛人になります。「わたし」が15歳半のときでした。母と上の兄は仲良くし、中国人との関係を知った母は「わたし」に「まるで娼婦だ!」と憎みます。そして、その中国人が死にます(小説上とはいえ、彼女が殺しました)。
彼女は似たような設定の小説『北の愛人』も出版します(わたしは未読)。『エミリー・L』を読んだところ、あまり面白くなくてページを飛ばして訳者あとがきを読むと、タイトルのエミリー・Lは19世紀の詩人エミリー・ディキンソン(1830~1886)だそうで、家族そろって敬虔なキリスト教徒にもかかわらず、彼女だけは「恩寵拒否」の人でした。
None may teach it --Any--
'Tis the Seal Despair--
An imsperial affection
Sent us of the Air--
When it comes,
the Landscape listens--
Shadows--hold their breath--
When it goes,
'tis like the Distance
On the look of Death--
その正体はなんびとにも皆目不明
それは絶望という封印
虚空から送られてきた
荘厳な苦悩である
それが訪れてくる時、
風景は耳をそばだて
もの影は息をひそめる
たち去ってゆく時は、
死者の相貌にあらわれる
遠ざかりを思わせる
時代が時代なので、周囲の人たちから爪弾きにされても、エミリーは自分の気持ちを絶対に曲げませんでした。彼女はこう書きます、「狂気昂じて至高の正気」と。デュラスは自分とエミリーとを重ねました。
『エミリー・L』のLは、『ロル・V・シュタイン(の歓喜)』の頭文字Lです。この架空の名前は「ロル=ROLL=紙(パー)」、「V=はさみ(チョキ)」、『シュタイン=石(グー)』といったじゃんけんのことです。こうしてデュラスは言葉遊びと想像を深めていきます。
デュラスが興味を持ったのは、ヘミングウェイやジャック・ロンドンなど、自殺した男性作家でした。理由はわかっていませんが、わたしにはわかります。デュラスはすべての男たちを憎み、想像のなかで殺していたのですから(このエピソードはヤンの口述筆記のなかで出てきます。アルコール依存症で朦朧となった彼女に自殺した男性作家の自伝を朗読すると、彼女は夢中で聞き入っていました)。
彼女が書いた小説はすべて「嘘、作り話、妄想上のこと」で、事実ではありません。ですが、彼女が繰り返し繰り返し同じ設定の小説を書くのは、裏を返せば、その事実を否定するために何度も何度も壁を塗るようなものです。女性作家が小説内で肉体関係の描写をすると、「これは事実ではないか?」とゲスい出刃亀のような心理に陥りますが、デュラスの小説を読めばわかります。彼女は強迫観念のなかで書き続けました。書かずにはいられませんでした。
もうひとつ、訳者あとがきでわたしがメモしたのは、モーリス・ブランショ「書くために死なねばならぬ。だが、死ぬためには書かねばならぬ」でした。これも、彼女の作家人生を端的に表現した言葉です。
いまわたしが読んでいるのは、ヤン・アンドレア『マルグリット・デュラス 閉ざされた扉』です。デュラスと38歳も年の離れたヤンと恋人関係になったデュラスは、アルコール依存症でぼろぼろになり、指の震えが止まらなくてヤンが口述をとったのでした(後に『死の病い』として出版)。こうして、過去は事実か想像かわからなくなりました。過去は過去、すべては虚構、虚無だけが通り過ぎます。そして、すべてはあなたが想像するしかありません。
(2021年11月14日)
MtFトランスジェンダーと女装男はどう違うのか?
ジョン・アーヴィング原作の映画『ガープの世界(1982)』のあらすじと登場人物を簡単に紹介する。主人公ガープとその母親ジェニー、ガープの妻ヘレン、元フットボール選手のロバータである。
***
学生時代のガープが自伝小説を書こうとしたとき、看護師のジェニーは「私の人生を勝手に書かないで」と彼を制し、街角に立つ娼婦にインタビューしたりして、自叙伝『性の容疑者たち』を出版しブレイクする。小説家になりたいガープは、むしろジェニーの私生児として有名だった。世はフェミニズムの時代、公民権運動の時代である。ジェニーの自宅には徐々に女性たちが集まってきて、女性だけのコミュニティを作ったのだ。
とある事件が起きる。11歳の少女エレンがレイプされて舌を切られる事件だ。被害者の少女が告発しても直接訴えることができないだろうと残酷で卑怯な犯人は思ったのだ。事件に抗議するコミュニティはみな怒りに満ちた顔で筆談をし、なかには自分で舌を切って抗議する極端な女性もいた。男に対して敵意を抱く女性たちは、ガープのことも嫌っていた。そのコミュニティのなかでSRSを受けたロバータだけは彼と友好的に接した。
あるとき、フェミニスト政治家の講演の応援をするために出かけたジェニーは、集会の広場で暗殺者の銃弾に撃たれる。
ジェニーの葬式には多くの人が出席した。ジェニーの支持者たちは、女性のみで追悼式を開くと言い出し、ガープの出席を認めない。ロバータはガープを女装させ、追悼式へ出席させてやる。
追悼式に集まった女性たちは男を憎んでいた。そのなかには幼馴染のプーもいて、ガープを目ざとく見つける。ロバータは女性たちからガープを守り会場から出す。裏口へ案内してくれたのは、なんとあのエレンだった。彼女は本の出版を喜んでくれており、ガープは感動する。
***
あらすじは以上。さて、ここで問題。男をヘイトする女性コミュニティは、なぜロバータを受け容れてガープを排除するのだろう。ロバータもガープも、同じ女装の男性ではないのだろうか。
答①:ロバータもガープも同じ男だ。あなたがこう答えたなら、あなたはTERF(Trans-exclusionary radical feminist:トランス排除的ラディカルフェミニスト)かもしれない。シスヘテロ男性もMtFトランスジェンダーもどちらも男性だろう。と、あなたは大雑把に、乱暴に答えるだろう。あなたは<男性における性差>というものの微妙な違いが見えていないのかもしれない。
答②:ロバータもガープも同じ男だけど、ロバータは女性名を使用し、セクシーな色どりの服やヘアメイクで着飾っていても、ロバータのほうがむしろガタイが大きいし、ガープのほうが背が低い。ロバータは男性の恋人がいて、ガープは結婚して子どもが二人いる。セックスは同じ男でも、「性的志向&性自認(SOGI:Sexual Orientation & Gender Identity)」は違うのだ。
百歩譲って、TERFなるものたちは「社会的弱者である女性が集まっている場所、たとえばDVのシェルターに、レズビアン・コミュニティに、レディース・バーに、女子大に、女子便に、銭湯に、なぜわざわざMtFトランスジェンダーが入ってくるのか?」と(主にネット上で)憤っている。まさにその通り。
で、あなたは実際DVシェルターにいたのか? レズビアン・コミュニティには? レディース・バーは? 女子大や女子便や銭湯に、MtFトランスジェンダーが割り込んでくるのを、あなたは目撃したのだろうか?
もしかして、ネットの言葉に影響されてないか? 想像力豊かなのは結構だが、証拠はないはず。
わたしは実際、レズビアン・コミュニティでMtFトランスジェンダーを目撃したことがある。また十数年前、某レズビアン・コミュニティではスタッフ同士で「もしトランスジェンダーが来たらどうするのか? 追い出すのか、それとも受け容れるのか?」という議論があったという。
たとえば、「女性を愛する女性」が出会いを求めて参加した。そのとき初めて会ったのは「レズビアン」と自称しているけれども外見上普通の男性である。びっくりした参加者は、もう二度とそのコミュニティには来ないだろう。彼女はずっと怯えているそうだ、本当は女性との出会いを求めたいのだけど、男性に出会うのはもうこりごり。
もしレズビアン・コミュニティに男性がいても、わたしは怯えることはないので、以上は想像である。だがあなたたちTERFの想像は、わたしの想像と異なる。TERFのは妄想で、ただの譫言だ。
もし「女性たちが安心できる場所」で確かに「男性」がいたのなら、なぜ怯える必要があるのだろうか? それは「不安」でも「恐怖」でもない、ただの「混乱」である。
あなたたちTERFが「女性とは何か? 男性とは何か?」という性的概念の境界が、性的常識が、「ほんとうのわたし」ががらがらと崩壊するのが怖いのだ。性はグラデーションではなく「女か? 男か?」、常にゼロか100である。極端な思考だ。
あるとき、レズビアンの友人が話していたのを覚えている。彼女は初めての相手とセックスした。その相手はDSD(性分化疾患)で、身体は女とも男とも判別できなかった。レズビアンの友人は果たしてレズビアンになったのだろうか。
また、外見的には典型的な女性に見えるのだが、外性器の形はヴァリエーション豊富だ。クリトリスなのかペニスなのか判別しにくい。男性のペニスよりも大きなクリトリスを持つ女性は、世のなかにはたくさんいるだろう。
「性別はセックス(身体的性役割)ではなく、つねにすでにジェンダー(社会的性役割)である」と頭ではわかっていても、肝心な場合には必ず「相手の性器(セックス)は男か? 女か?」と基本的な判断(習性)がつい働いてしまう。「相手の性器(セックス)」が男女どちらか気になるのは、同時に「わたしの性器(セックス)」が男女どちらなのかが気になるのだ。
つまり、あなたがどんなに自由でいても、どんなに知識があっても、性の常識の砦を崩壊するのが最上の恐怖なのだ。
たとえばもし、あなたが乳がんで乳房を失い、子宮がんで子宮と卵巣を失っても、果たしてあなたは堂々と「女性である」といえるのだろうか。
(2021年11月9日)
本の花束(14)カリン・ボイエ『カロカイン』(2008年、みすず書房)
ウィキペディアの「レズビアンの作家一覧」に、カリン・ボイエ(1900–1941)があり、『カロカイン 国家と密告の自白剤』があったので、さっそく図書館で借りて読みました。本の裏表紙にはこう書かれています。
地球的規模の核戦争後、人びとは、汚染された地表から地下へのがれ、完璧に全体主義的な警察管理体制のもと築き上げられた<世界国家>の同輩兵士として暮らしている。言動を監視する<眼>と<耳>が職場や住居にはりめぐらされ、夫婦や親子の絆は捨て去るべきものとされる。情愛と忠誠の唯一の対象は<世界国家>でなくてはならないのだから。
模範的同輩兵士で、化学者のレオ・カールは、その液剤を注射されると心の奥底に隠された思いや感情を吐露してしまう自白剤<カロカイン>を完成させる。人びとの思考や感情の統制までも可能にできる<カロカイン>の発明によって成功への階を着実に昇ってゆくかに見えたレオ。強いられた自白はしかし、やがて思いもかけない方向へと展開をみせる……
20世紀スウェーデンの国民的詩人ボイエの、散文の代表作。
「スウェーデン」「国民的詩人」「レズビアン」「散文の代表作」とあっては読まずにいられない『カロカイン』(カールが発明したコカイン?)ですが、現代日本のお笑い番組では「(芸人たちに)自白を強要させる」のではなく、「番組の枠を読み取り、自ら進んで自白する(ウケる笑いを取る)」というスーパーサバイバルな状況ですから、どちらがディストピアか想像するまでもありません。ボイエのディストピアは少々温い気がしますが、化学者レオ・カールの語りによって綴られる小説を読んだら、これがメモらないわけにはいきません。わたしがいま書いているテーマ(家族・親子愛の崩壊の危機)と超フィットしてる! そして美しいこの響き! 驚きました。
勝ちたいと念じながら、つねに負けつづける。[…]わたしはこそこそと逃げて身を隠そうと必死だった。そのくせ、ぞっとするほど見透かされていると感じていた。しかも彼女のほうはどこまでも謎のままとどまる。[…]魅惑にみちて、力強く、超人的ですらあり、なおも永遠に不安をかきたてる謎として。その謎めいた在りかたがおぞましい優越をリンダに与えた。
カリン・ボイエ『カロカイン(1940)』
わたしは一度開いた『カロカイン』を閉じ、ネット検索しました。日本語ではボイエの情報はほぼありませんから(日本語訳されてるのは『カロカイン』のみ)、スウェーデン語で邦訳し、その「生きざま」を鑑賞・分析します。小説を読むにはたいへん紆余曲折ですが、より魅力的な作家はバックボーンを詳細に調査してから作品を読みます。これがわたしの読書作法とでもいうべきなのでしょうか。
とりあえず、ウィキペディア(スウェーデン語ヴァージョン)の荒削りな邦訳から入ります(たまに不自然な表現もあります申し訳ありません)。途中で訳者あとがきがスライドします。ごちゃごちゃですみません。
カリン・マリア・ボイエ(1900-1941)はスウェーデンの作家、詩人、翻訳者です。彼女は詩でもっともよく知られていましたが、小説や短編、エッセイも書いています。散文作品のなかではディストピアSF小説『カロカイン(1940)』がもっとも注目を集めています。
土木技師の父フリッツ・ボイエ(1857–1927)と、母シグネ(1875–1976)のリリジェストランドとして生まれ、どちらも裕福な家族から来ました。フリッツの父は卸売業者のエドゥアルト・ボイエでした。カリン・ボイエは、自分自身が「過度に模範的」に管理されていると考えました。1907年、彼女はヨーテボリのマチルダホール学校に通いはじめましたが、学校では高学年でした。二人の弟はスヴェン(1903–1974)とウルフ(1904–1999)です。父親がストックホルムのスウェーデン保険検査官に転職したため、家族は1909年にそこに引っ越しました。 1915年、家族は現在のスヨーダルスギムナシエトがあるフッディンゲに定住しました。そこには白樺、まっすぐに育った松、樫の木が生い茂る森の丘があり、白い結び目とモールディングが施された高層住宅が建てられていました。家族は彼らの新しい家に「ビョルケボ」という名をつけました。そこで彼女はたくさんの若者の詩、短編小説、演劇を書き、水彩画を描きました。カリン・ボイエの絵についてあまり知られていないのは、彼女が神話上の人物で非常に個人的な水彩画を描いたからです。これらは後に、ユージン王子のヴァルデマーシュッデの部屋全体を占領しました。
1920年、ボイエはストックホルムのオーリンスカ学校を卒業し、1921年に小学校の教師として働きました。その後ウプサラに行き、ギリシャ語、北欧の言語、文学史を学びました。1918年にフォーゲルスタッドのクリスチャンサマーキャンプで、アニタ・ナトホルストに会い、ウプサラで再会しました。 7歳上のナトホルストは、ウプサラ大学で神学と人文科学を学びました。ボイエは1928年にストックホルム大学で哲学の学位を取得して卒業しました。 その後、過度の運動と激しいストレスにより、彼女はウプサラを離れることを余儀なくされましたが、正確な背景は不明です。さらに彼女は女子学生協会の会長であり、学生雑誌エルゴに書きました。
1922年、彼女は詩集『雲』でデビューしました。この詩集は、若者の神への陰気、人生の欠点、そして彼女自身の未来を伝えました。しかし、彼女の特別な特徴やモチーフもありました。正確には、流れやすい韻と韻を書く傾向(彼女がウプサラのアイスランド語でエドダンの詩を読むようになったときに強化される)が目立ちます。しかし何よりも、強調された音節が交代するなど、特別なリズムが印象的です。次の詩集『ゴムダランド(1924)』と『ヘルダーナ(1927)』で、彼女はキリスト教の動機に基づいて、勇気、戦い、犠牲を呼びかけています。 1925年に、彼女は学生自治会の春のパーティーで有名なスピーチをしました。最初の小説『アスタルト』は、1931年に北欧のノーベル賞コンペティションで受賞しました。 1927年、カリン・ボイエは社会主義雑誌『クラルテ』の編集委員会のメンバーになりました。彼女はまた雑誌『スペクトラム』を共同設立し、ヨセフ・リウキン、エリック・メスタートン、グンナー・エケロフとともに編集スタッフ(1931-1932)の一部でした。スペクトラムでエッセイ『論理を超えた言語』が出版され、そこで彼女は精神分析に基づいて新しい詩的で象徴的な言語を求めました。彼女はまた、このイニシアチブのために資本の一部を寄付するようになりました(彼女の父親は1927年に亡くなり、彼から受け継いだお金で経済的に自立しました)。 1931年に彼女はナイン協会に選出されました。
1932年から1933年のベルリン滞在中、彼女は以前より明確な方法で同性愛者と一緒に暮らすための一歩を踏み出しました。レイフ・ビョルクとの結婚は3年足らずで破局し、スウェーデンに戻ったとき、友人が経験したように彼女は変化しました。よりエレガントで、クラルテの積極的なマルクス主義側にあまり興味がなく、おそらく以前よりも脆弱でした。しばらくして、彼女は若いドイツ系ユダヤ人の女性マーゴット・ハネルを招待しました。彼女はマーゴット・ハネルと出会い、ベルリンに「誘惑」しました。まだスウェーデンでは同性愛が犯罪だった時代です。しかし、ボイエのアニタ・ナトホルストへの深い愛情には決して答えられませんでした。 ボイエはデビュー小説の時からレズビアンやバイセクシュアルの側面を自覚していたのでしょうが、男とともに生きる必要があるように見えたため、しかし実際には受け入れがたく、性的対象は女性でした。その問題について公然と話すことは困難でした。学生時代からボイエを知り、彼女のイメージに強い影響を与えるようになったマルギット・アベニウスは、この問題を彼女の10代の詩からたどっています。すでに10代のころに書いた詩や伝説のなかで、ボイエは男性のヒーローと同一視することがよくあり、彼らの犠牲的な行為はしばしばエロティックなものとして見られます。アベニウスは、自分の選択、さらには無意識の選択に忠実であることと、自分の信念(ボイエ自身の言葉で「まっすぐに生きる」)と、私たちが引き受けたい外部の道徳的要求(フロイトの超自我)との間の闘争は重要である、と信じています。デビュー本以降の対立の線――彼女の禁じられた欲望に対するボイエの洞察と多くの関係があります。ボイエ自身も『クリス』で同様の解釈をしていますが、ベルリンの年の直後に書かれているため、ボイエが1921年初頭に経験した危機の結論として、その小説を簡単に見ることはできませんでした(そして彼女自身が最初の分析を行った、彼女の友人アグネス・フェレニウスへの手紙に書いてあります)。ベルリンにいる間、彼女は精神分析的治療も受け、ナチズムの突破口を間近で目撃することができました。
カリン・ボイエのもっとも有名な詩は、おそらくコレクションの「はい、もちろん痛い」です。ツリーのために、コレクション『囲炉裏』の「動き中」がそれに続きます。散文作品のなかで最もよく知られているのは、部分的に自伝的小説の『クリス』とディストピアの『カロカイン』です。 エッセイストとして、彼女は主に文学分析とモダニズムへの精神分析的影響を扱い、評論家としても活躍しました。カリン・ボイエは、スウェーデンの第二世代のモダニストの1人です(最初の波であるペール・ラーゲルクヴィストとビルエル・シェーベルグの後)。
『七つの大罪、その他の遺稿詩集(1941)』に収録された詩「信頼は生きのびるか」――第二次大戦が始まったとき、ボイエはラジオでこの詩を朗読しました。信じていたものがことごとく崩れ去っても、信頼がことごとく裏切られても、うろたえて不安や絶望に身をゆだねる必要はない。おのずから生まれて育つ自分自身への信頼に賭けてみようと。植物の神秘主義とでもいうべき表象は、世界樹(ユグドラシル)の神話に親しんでいる北欧人の心情に訴えるものがあったのではないか。人間の住まう世界ミズガルズを支える巨大なユグドラシルは、神々の終末(ラグナロク)に先立って滅びる定めであるが、それでもなお地中深くに根を下ろし、神々の住まう天にむかってゆたかな葉むらを茂らせる。
われらの周囲では、すべてが壊れていく、
これからはさらに手ひどく壊れていく、
ただひとつの石も残らないほどに、
われらの足を支える、たったひとつの石さえも、
なのに、いかにして信頼できよう、
なにひとつ信頼すべきものがないのに。
いかにして信頼は生きのびるのか、
なにひとつ根がないというのに。
それは根なのか。
それは種なのか。
世界樹(ユクドラシル)でさえも、
そこから生え育つというのか。
そのとき、われらの運命はゆだねられよう、
寡黙な心たちのなかに。
かれらの沈黙のゆえに、
暁はまだ来るだろうから。
ラジオのまえでスウェーデン国民に自己への信頼を呼びかけた詩人は、しかしながら、自分自身を説得することはできなかった。1941年4月23日、カリン・ボイエは消息を絶つ。数日後、森のなかで発見される。自殺だった。
アリングソースのノルビー地区にあるこの岩の上で、カリン・ボイエは1941年4月27日に死んでいるのが発見されました。岩のすぐ向こうでは、自然の景色とアリングソースの街を背景に群がっていました。 カリン・ボイエは、1941年4月23日に睡眠薬の過剰摂取(自殺?)の後、死亡したのです。ゴーセンバーグ国立公文書館の文書によると、カリン・ボイエの死体は、アリングソース郊外の丘の上の大きな岩の上で発見されました。彼女は癌で亡くなっていた友人のアニタ・ナトホルスト(1894-1941)を助けるためにアリングソースに滞在し、その最後の数ヶ月間に、ボイエは時々ストレスを感じ、ますます不安定な状態で彼女に会った友人が受け取った彼女自身の手紙と、その後の声明によって判断していました。カリン・ボイエが発見されたノルビー地域の岩は記念石にされており、アリングソースの観光地図に載っています。カリン・ボイエは、ヨーテボリのオストラカーコガーデンに埋葬されています。彼女のボーイフレンドであるマーゴット・ハネル(彼は彼女と一緒にアリングソースにいなかった)も、ボイエの死後1か月で自分の命を奪いました。アニタ・ナトホルストは同じ年の8月に癌で亡くなりました。
ボイエの死の翌年、死後の賛辞の本、『カリン・ボイエ――記憶と研究』(編集:マルギット・アベニウス、オロフ・ラーゲルクランツ)と彼女の著者の友人の何人かからの寄稿が出版されました。この本の最後には、ヤルマール・ガルバーグの詩『死んだアマゾン』がありました。これはボイエの死の直接の印象の下で書かれ、1941年5月にBLMで以前に印刷されたものです。それは、彼女の人生と仕事における英雄的で反抗的で悲劇的なものの厳密な定式化を与えました(そしてドイツとギリシャの軍隊が同時にスパルタの戦士が最後の男と戦ったテルモピュレで戦争しており、この人生に比喩的に反対する。それは古代ギリシャの自由である)。この詩は、ボイエの英雄的なイメージの古典的な表現として見ることができます。 ボイエの死後出版された詩集の詩『七つの大罪』(「散らばって分割されたものすべて」)は、詩篇と歌76にいわゆる読書詩篇として含まれています。しかし、最終的に採用された1986年の賛美歌には含まれていませんでした。
カリン・ボイエの像は、ヨーテボリ近くのヨーテボリ市立図書館に建てられています。彫像は1980年以来フッディンゲにも存在しており、自治体は1998年から毎年カリン・ボイエ文学賞を授与しています。別の像はストックホルム大学にあり、カリン・ボイエの木はウプサラにあります。
近年、ボイエの人生と執筆は様々な研究努力と出版された本の主題となっています。カリン・ボイエ協会(1983年に結成)に加えて、ポーリーナ・ヘルゲソンとピア・クリスティーナ・ガルデは、とりわけ、ボイエの背景と関係をさまざまなテキストや伝記の本で紹介しています。
2013年には、ジェシカ・コルタージャーンの最高の日、1932年から1933年のベルリンでのカリン・ボイエの時代に基づいた伝記小説(コルタージャーン自身の言葉で「文学ファンタジー」)である『渇きの日』です。
2015年に、ヨハンナ・ニルソンによって書かれた『カロカイン』の続編は、『より環境に優しい深さ』という名で登場しました。2017年に出版されたカリン・ボイエの最初の主要な伝記であるジョアン・スベジェダール『新しい日の夜明け』は、1950年からの純粋さの影響を受けたマルギット・アベニウス以来のカリン・ボイエの作家生活が書かれています。
(2021年10月23日)
本の花束(13)佐藤亜有子『花々の墓標』(ヘルスワーク協会、2008年)
2016年の日記に、佐藤亜有子が亡くなった、と書いてあり、わたしは自分で書いたものに自分で驚きました。佐藤亜有子という作家も知らなければ、彼女が亡くなったことすら知りませんでした。なぜ無名の作家が死亡した件を日記につけていたのでしょうか。5年前の自分はなぜか気にかかったのだと思います。それでもまだ作品は読んでいませんでしたが、先日さっそく『花々の墓標(2008)』を読みました。
1969年生まれの彼女は、わたしと同世代です。東大仏文科卒で、翻訳業のかたわら小説『ボディ・レンタル(1996)』で第33回文藝賞優秀作に選ばれますが、2013年、アルコールを併用した急性薬物中毒で死去します。享年43。彼女は全部で10作品を遺しました。そのなかの一冊が『花々の墓標』です。これは小説ではありません。自叙伝でもありません。
衝撃的な作品で脚光を浴びたニキ・ド・サンファルは、あるインタビューで、もしわたしがアーティストにならなかったら、テロリストになっていただろうと語っている。性虐待――中でもとくに親権者から受けた性犯罪の被害者が抱く怒りや暴力衝動は、人の想像を絶するくらいとにかく激しいものなのだ。わたしも彼女と同様に、作家でなければ通り魔か狂人か、殺人犯になっていただろう。わたしは男を殺すこと――できることならすべての男を殺害することを夢想せずにはいられない。ギリシャ神話の最高神で好色漢のゼウスにも、ハーレムを持つ獣のオスにも、わたしは本当に吐き気を覚える。だがわたしは、なにも、世界の半分を占める男の性と敵対するべく生まれたわけじゃない。それどころか、わたしは自分に取り憑いている男たちへの殺意に苦しむ。なぜここに愛はないのか、なぜわたしは誰とも愛し合えないのか――そう思えば思うほど、わたしの生への絶望感がますます深くなっていく。
佐藤亜有子『花々の墓標』
幼少のころ、ニキは実父のペニスを舐めさせられたといいます。父の名前が象徴的で、“ド”は貴族の称号、“サンファル”はフランス語で“聖なるペニス”。女子どもは家父長制の犠牲者たちなのです。
佐藤亜有子の幼少期にも、実父から性的虐待を受けた記憶がありました。同じころ、姉もまた実父から性的虐待を受けました。姉は東京の音大に入って一人暮らしをしますが、学生生活が破綻した姉は、退学して実家に戻って精神科に入院します。泣き、喚き、暴れて、姉は人格がどうにかなってしまったのです。診断名は境界性障害。当時、亜有子はかろうじて精神のバランスをとっていました。彼女は姉よりも症状が軽かったのですが、母と姉と時間をかけて話し合いました。
姉の顔は叔母(父の姉)に似ていたので、父は姉にこう言ったのです。「もしもこの世にお前とお父さん二人きりだったら、お前はお父さんの子を産むんだ」と。そして、父と姉が性交しているところを、母が目撃しました。母もまた幼いころ、近所の中学生たちに集団で犯され、実兄とも一方的に肉体関係を持たされました。
姉の話から、「わたしは愛されてないんだ! 父に無料で身体を触らされたわたしは幼い娼婦だったが、父は姉を愛していたんだ!」と、父との歪んだ愛情から狂気の嫉妬が生まれます。母の話から、「佐藤家の女は性的に搾取されるのが因習的な呪い」だと、運命のループから逃れられない無力感を抱きます。何もかも父が悪い、父のせいだ、と憎むと同時に、父から愛されていない、わたしは必要ないんだ、と自暴自棄になるのです。
彼女にとっての小説は、ニキのような「作品」として、自己治癒を目的としていましたが、一人ではもうどうすることもできないと自覚して、精神科医・斎藤学のところへ通い、似たような患者(あるいは被害者)たちとグループ・セラピーに参加します。そのセラピーのイメージワークで彼女が見たのは(白昼夢であるらしい)、彼女自身の血まみれの死体でした。たぶん誰かに殺された(あるいは父に何度も性的に虐待された)のでしょう。
わたしはいくら先生の言葉どおりに春のイメージを浮かべてみようと試みても、晩秋か冬の森しか見えなかった。日差しはまだある時間帯だが、空気は乾いて肌を刺すほど冷たくて、すっかり木々の葉が落ちて、裸になった枝の影が、黒く不気味に絡み合っている。もう生き物の声もない。そんな荒涼とした景色が、どう払っても頭の中から離れない。そしてわたしは落ち葉の積もった地面の上に、服が裂かれて肌もすっかり乾いた血や泥にまみれた、女の死体を目にしていた。その虚ろに見開かれた目が、ショックのあまり茫然として凍りついた表情のまま、わたしを見つめ返してくる。
[…]
あなたは、自分の死体をどうしてあげたい? わからない、彼女はもう死んじゃったから、どうすることもできない――そういいながら泣きじゃくるわたしは、完全な混乱状態に落ちていたので、自分がなにをどう言ったか、あまり整理できない。ただ断片的に、死体はすっかり傷だらけで、そこに置き去りにされたまま、まだ誰も見つけてくれない。服はずたずたで、肌も泥まみれ、血まみれ。誰も死体の目を閉じてくれない。傷ついた体をちゃんと洗って、きれいな服に着替えさせて、その死を悼んでもくれない。そんなことを嗚咽の合間に、口走ったように思う。
いつの間にか、わたしの周囲には、さいわい全員女性だった参加メンバーが集まってきていて、ならわたしたちが、ちゃんと体を洗ってあげるよ、傷もきれいにして、服も着替えさせて、ちゃんとお祈りしてあげる――そうつぎつぎにわたしに声をかけてくる。わたしは感謝を伝えるつもりで、その都度うなずきながら、ふたたび死体をどうしてあげたいと尋ねてきた先生に、暗い地中に埋められるのはいやだから、その代わり、そのまま地面に横たえておいて、花で埋めてもらいたい、と答えていた。いろんな花。色鮮やかな花々や、とても香りのいい花。それでわたしの死体を、すっかり覆ってもらいたい。
すると周囲のメンバーが、じゃあわたしは、スミレを持ってきてあげる、わたしはカトレア、わたしはヒヤシンスと言って、言葉でわたしに献花してくれる。傷だらけで汚れてしまったわたしの死体が、そこに集まったみんなの手で洗われて、服もきれいにしてもらって、きれいな花々で埋められていく――そんなイメージで、わたしはすっかり過度の興奮で疲れきっていたものの、まぼろしの花びらのひんやりとした感触や香りで、心は徐々に鎮まっていった。もう大丈夫? と訊いてきた先生にうなずいたわたしは、そのイメージを抱いたまま、その場で眠りに落ちていった。
春の森のイメージに失敗して、自分の他殺死体を見る。その殺伐としたイメージは、どう見ても「幼少期に性的虐待を受けていた自分」で、セルフイメージの修正をみんなに手伝ってもらう。みなそれぞれ傷ついているが、そのぶん、同じ仲間にはとても優しくて思いやりがある。感動的なワンシーンでした。
最初は思いつきで「パーツごとに売春する最高学府の女子大生」を小説に描き、それから年一冊のペースで発表していましたが、5年の沈黙のうち、『花々の墓標』が出版されました。版元は斎藤学が顧問を務めている医学書中心の出版社で、彼が解説を書いています。
[…]
治療で接した彼女は児童期性的虐待の被害体験を持つ特有の症状(解離性フラッシュバックを始めとする解離性障害)を抱えていた。彼女の著書にもその影響を読み取ることができる。解離性障害とは意識野に貯蔵され編集された記憶とは別種の生々しい記憶が日常現実にしみ出す現象のことである。「解離」とか「意識野」とかいう言葉を用いて現代の外傷性記憶理論の基礎を築いたのはフランスの心理哲学者で精神科医でもあるピエール・ジャネで、彼は意識野から排除(解離)され「記憶という編集作業」を受けないまま「生々しさを保ち続けている過去の体験・感覚・感情」が何らかのきっかけで甦るものと考えていた。
ジグムント・フロイトによるオイディプス葛藤説が世を覆うようになってから、ジャネの解離理論は忘れられ、解離性フラッシュバックや多重人格は犠牲者を騙る者の「空想」と片づけられてきた。しかし1960年代後半から始まったベトナム戦争が事態を変えた。父親からの性被害の後遺症に悩む女性たちの症状は「空想」とされて屑籠に入れられたが、国家の要請に応えて出征した青年たちの戦争外傷後遺症(映画『ディア・ハンター』『タクシー・ドライバー』などの映画がその実態を明瞭にしている)まで「空想」とするわけにはいかなかったからである。こうしてPTSDが疾患単位として登録されるようになり、「ジャネの復権」とも呼ぶべき外傷理論の精緻化が進んでいる。さらに外傷体験を災害・事故・戦争などとの遭遇体験を指す「単一性PTSD」と、家庭内暴力や児童虐待・近親姦虐待のような閉所で長時間続く外傷体験後遺症を意味する「複雑性PTSD」とを区別して把握するべきだという意見もある。こちらの方は精神科医一般に受け入れられているとは言えないが、わたしはこの意見に賛成だ。
要するに佐藤さんは複雑性PTSDを抱えた人だと考えたので、そのための治療を行った。その方法は「得も言えぬ恐怖」で語り難くされている体験を「敢えて語る」機会を与えることである。これを反復させることで「語り得なかった」(それゆえに自らのパーソナリティに編集統合されてこなかった)記憶は自分というストーリー(筋書き)の中に統合されるようになる。そのためであれば話してもよいし、描いてもよい。もちろん書いてもよいわけで佐藤さんには、「今まで書けなかったことを書く」ことを求めた。
その結果を読むことができたのは04年の春頃のことだったと思う。今目にしているものよりも荒削りで、特にエンディングの死体は枯葉の中に放置されていたと記憶している。この作品がそのまま商品として流通するとは思わなかったが、それは内容のせいではない。これを特異な文学作品として流通させるだけの度量が、今の日本社会にはなかろうということだ。案の定、商品としての出版は無理とのことだったので、こうした作品や書物のための受け手であるヘルスワーク協会から出版することにした。作品の中で彼女の遺体は花に囲まれた『花々の墓標』となった。
自分が死ぬ夢は良い夢だ。それは現在までの自分が死に、それを葬る自分が新たに生まれつつあることを告げる夢である。自らの遺体を花で飾った「作家」佐藤亜有子の再誕生を悦びたい。
[…]
作品と呼ばれる象徴化作用の結実は、絶望を伴う試行錯誤の中で行われ、おそらく描いても描いても(書いても書いても)「それらしいもの」にならないといったものなのだろう。それが芸術家に固有の、飽くことなく続く「失せ物探し」の反復となる。このとき、外傷体験の反復という「自傷」に使われるはずだったエネルギーは、人びとが見る(読む、聞く)という現実に向かって「作品」を投げ込むことに消費される。
芸術家の作品とリストカット愛好者の切創写真との違いは、ここにこそあると思う。音なり絵なり文章なりの形で表象化されない「自己境界の確認行為」つまり「皮膚カット」、「ボディ・モディフィケーション」(刺青やピアシングや性器変形を含む)の類は、生きることに伴う痛みと自己喪失という現実にべったりくっつき過ぎていて象徴化の労苦を通過していない。再びフロイトの引用になってしまうのだが、彼は『詩人と空想すること』という論考の中で、白昼夢を見る夢想家は現実を無視して願望的幻想の達成という快楽だけを貪っていればいいのだが、芸術家となると作品として現実へと舞い戻らなければならない。
この点で作家・佐藤亜有子は今(08秋)苦しいところにいる。文藝賞で作家として世に出てから03年まで毎年一冊のペースで作品が出版され、そのうちのひとつでは芥川賞候補にもなった。しかし、04年に書いた自伝的小説は河出書房新社から出版されなかった。その作品(『花々の墓標』)は、それを世に出すことそのものが「自傷」になりかねない危うさを孕んでいるので、担当編集者が出版を止めさせたというのもわからないではない。作家・佐藤の終わりを恐れたのだろう。そこには「犯す父」を殺しきれない(内面化しきれない)亜有子の悲鳴そのものがさらけだされていて、あたかもリストカット写真を見るかのようだ。しかし特異な文章力の紡ぎ出す物語世界の迫力は圧倒的である。「これこそ言語化されたニキの世界」とわたしは思うのだが。
作家・佐藤亜有子はこの作品を契機に思い切ってマルグリット・デュラスの歩いた道を進めばいいのだと思う。それには、まず頑強でなければならない。自己破壊の道に迷い込まないですむ程度に。
デュラスはモンスターのような母を憎み、それについて書いては書いているうちに母とそっくりなモンスター女になった。佐藤にとってのモンスター父は彼女に取り込まれて、どのような亜有子を生むのか。それを見たい。
いま、わたしはデュラスを読みたいと思っています。その前に、佐藤亜有子の全作品を、追悼の意味を込めて読了し、彼女の作品の価値の復活を諮りたいと思います。コロナ第6波が来るか来ないかにかかわらず、映画やドラマのネット配信は、今後も企画となる脚本を待望していると思います。世間に伸るか反るかという動向の波に、夭逝した作家・佐藤亜有子が忘れられないうちに。ふたたび屑籠に入れられないうちに。
(2021年10月14日)
本の花束(12)小池昌代『黒雲の下で卵をあたためる』(岩波書店、2019年)
詩の言葉はとても光り、ときには胸にひどく刺さりますが、小説となるとさほど光らない人がいます。中島みゆきです。わたしは40年くらい(最初はたぶん小4)彼女のファンでして、深夜放送も毎週欠かさず聴いていました。大学受験の年になると、彼女は深夜ラジオを「中退」(「卒業」と言わないところが彼女らしい)し、フォークの曲調をロックにアレンジしたり、小説をいくつか出版したり、精神的にも肉体的にも行き詰まりを感じたらしく、いわゆる「葛藤」をしていたらしいのです。それが、シアターコクーンの『夜会』(独り芝居ミュージカル?)が始まると、何だかしっくりしたように落ち着いてきました。ちなみにわたしは一度も行けていません。ファンクラブに入っていようがそうでなかろうが、チケットの入手が非常に困難なのです。『夜会』は毎回満員御礼だと聞きました。
彼女の初期の作品に『エレーン』があります。当時、彼女と同じアパートの住人が殺されました。被害者かつアパートの住人はセックスワークの外国人でした。それがとてもショックだったと、何かで彼女が書いているのを読みました。それと同じころ、『エレーン』らしきもののモチーフが小説となりました。わたしは「あ、これはあの曲に違いない」と思い、読みましたが、『エレーン』ほど、心のなかをかき乱されることはありませんでした。もしかしたら、彼女の言葉ではなく、歌がダイレクトに訴えてきたのかもわかりません。
詩人・小池昌代は、比較的最近知りました。何を読んだのかわかりませんが(たぶん小説です)、とにかく読んで感化されて、わたしもついうっかり小説を書いてしまいました。何が感化スイッチになるのかよくわかりません。しかもなお、彼女の詩集は、なぜかまだ読んでいません。おそらく詩も、雷に撃たれたようになるかもしれません。期待はしていますが、どうも彼女の詩集に手を伸ばすことはしませんでした。どうやらわたしのなかで何かのタイミングをはかっているようです。
先日、別の本を読んでいて、小池昌代の名前が出てきました。詩を紹介する本でしたから、彼女の詩も出てきたと思います。ところが、わたしはなぜかエッセイ集に手を出してしまいました。それが『黒雲の下で卵をあたためる』です。
圧倒されました。「鹿を追いかけて」という冒頭のエッセイです。
[…]鹿の目は、わたしを見ていたのであったが、わたしを含むこの世界全体を、まるくくるむようにぼんやりと見ていた。それはいってみれば、宗教的な瞳だった。
そういう視線に出会ったのは、初めてだった。ひとの視線の多くは、わたしという人間を世界から選別し、意味を与えるために、そそがれるものだった。あるときはやさしく、あたたかく、賞賛の意味を込めて。あるときは鋭く、きびしく、非難や叱責をこめて。
エッセイ集は全部で30近くあります。文庫本なので、寝る前に1編ずつ読むつもり(もったいなくて一気に読めません!)ですが、読むとつい思うところがあり、そして書かないと気が済まなくなり、かえって覚醒してしまいます。これがわたしの性分なのです。読み終わるころには、彼女の詩を読むでしょう。わたしのなかで、いまさら「小池昌代ブーム」が来ています。いまさっきAmazonでこのエッセイ集をポチりました。
最後に、担当編集者がおそらく作成したと思われる、裏表紙の宣伝文を引用します。要約には最適です。
誰もが毎日見ている空の下で、あの黒雲の下で、今、何が起こっているのだろう? 詩人の鋭い感性と豊かな想像力から立ち現れる、誰もが気が付かなかった日常風景のなかの一場面。読む人はそこで、詩人にどのようにして詩が訪れ、また、詩人は詩をどのように読み感じているのかに、触れることができるかもしれない。フィクションとも思える、美しい日本語を通して、新しい経験へと誘う。
(2021年8月31日)
本の花束(11)ハンナ・アーレント『全体主義の起源』(みすず書房、2017年)
『ハンナ・アーレント(2013)』が岩波ホールで公開され、インディペンデントシアターだけに珍しくヒットしました。わたしも公開時に劇場で観て、DVDをさっそく買って何度も観ました。
内容はハンナ・アーレントがエルサレムでのアイヒマン裁判をすべて傍聴し、雑誌『ニューヨーカー』に連載します。それらを『エルサレムのアイヒマン――悪の陳腐さについての報告(1969)』――映画では「悪の凡庸さ」と訳していますが――として出版しました。とにかく悪は一見かっこ良くて憧れるが実は浅はかなものである、悪は根源的ではない、根源的なのはむしろ善である、という主張でした。
SS中佐でホロコーストの中心人物であったアイヒマンは、「これまでユダヤ人を殺せという命令は出していない」「上からの命令に従っただけ」と言い逃れをします。ナチスは官僚的な組織だと感じたアーレントは、「ユダヤ人虐殺という世界的に残酷な歴史を刻んだ悪は、まったく何も考えていない」と書いて、「正義」の側としては「この冷酷なナチ女!」と猛烈に批判し、彼女は世間から反感を買いました。確かにアーレントはアイヒマンを庇っているように読めたのですが、決して感情的にならず、冷静客観的に裁判の様子を書いたのです。
彼女はドイツ系ユダヤ人として生まれ、ナチスが政権を獲得しユダヤ人迫害が起こるなか、一度は逮捕される危険もありましたが、1933年フランスに亡命し、1940年フランスがドイツに降伏して、ユダヤ難民援助のソーシャル・ワーカーなどとして働きながら(ユダヤ女性ラーエル・ファルンハーゲンの伝記を仕上げ、反ユダヤ主義の研究を進めた)、翌年アメリカに亡命しました。その後習得した英語で多くの著作を書き、ドイツ語圏の作家の著作の英語への翻訳・出版にも携わりましたが、彼女が思考する際の言語はドイツ語でした。余談ですが、マルガレーテ・フォン・トロッタ監督は「アーレントの哲学的に思考する姿は、バルバラ・スコヴァが一番である」とのことで、彼女が採用されました(バルバラ・スコヴァは『ローザ・ルクセンブルグ』の主演を務めています)。
『全体主義の起源』を1951年に英語で発表し、それを加筆・修正したドイツ語版を1955年に刊行しました。「第1巻 反ユダヤ主義」「第2巻 帝国主義」「第3巻 全体主義」があり、ドイツ語版序文をカール・ヤスパースが書いています。大学時代のアーレントはカール・ヤスパースの教え子でした。彼が序文で「3巻の最後を最初に読めば結論がわかるから、全体の流れをよく把握できる」と書いてあり、わたしもそれに従って読みました。タイトルは「イデオロギーとテロル」です。以下、非常に長いのですが、引用します。
孤立は人間生活の政治的領域に関係するにすぎないが、独りぼっちであること(ロンリネス)は全体としての人間生活に関係する。たしかに全体主義的統治はすべての暴政と同様、人間生活の公共的領域を破壊することなしには、つまり人びとを孤立させることによって彼らの政治的能力を破壊することなしには存在し得なかった。しかし全体主義的支配は、統治形式としては、この孤立だけでは満足せずに私生活をも破壊するという点で前例のないものである。全体主義的支配は独りぼっちであること(ロンリネス)の上に、すなわち人間が最も根本的で最も絶望的な経験の一つである。自分がこの世界にまったく属していないという経験の上に成り立っている。
テロルを生む一般的な地盤であり、全体主義的統治の本質であり、そしてイデオロギーもしくは論理性にとっては、その執行者および犠牲者を作り上げるものである独りぼっちであること(ロンリネス)は、産業革命以来現代の大衆の宿業となっていた、そして前世紀末の帝国主義の興隆および現代における政治制度および社会的伝統の崩壊とともに鮮明になった、根を絶たれた余計者的な人間の境遇と密接に関係している。根を絶たれたというのは、他の人々によって承認され保障された席をこの世界に持っていないという意味である。余計者ということは、全然この世界に属していないことを意味する。孤立が独りぼっちであること(ロンリネス)の予備条件であり得る(あらねばならぬ、ではない)のとまったく同様に、根を絶たれていることは余計者であることの予備条件であり得る。それを生んだ最近の歴史的原因や政治の中で、それが演ずる新しい役割を捨象してそれ自体について見れば、独りぼっちであること(ロンリネス)は人間の条件の基本的な要求に背離すると同時に、すべての人間の生活の根源的な経験の一つなのだ。物質的感覚的な所与の世界についての私の経験すらも、私が他の人々と接触しているということに、つまり、他のすべての感覚(センス)を統制し制御しているわれわれの共通感覚(common sense 常識)に依存している。そしてこのコモン・センスなしには、私たちの一人一人は、それ自体として当てにできない不確実なものである自分自身の感覚的与件の特異性の中に閉じ込められてしまうだろう。われわれがコモン・センスを持つからこそ、すなわち一人の人間ではなく複数の人間がこの地球に住むからこそ、私たちは私たちの直接的な感覚的経験を信じることができるのだ。けれども私たちは、自分もいつかこの共通の世界を去らねばならないが、それでもこの世界はこれまでどおりつづいていくのだし、この世界の持続にとっては自分は余計な存在なのだということを想起するだけで、独りぼっちであること(ロンリネス)を、つまりすべてのもの、すべての人から見捨てられているという経験を実感することができる。
独りぼっちであること(ロンリネス)は孤独solitudeではない。孤独は独りきり(アロウン)でいることを必要とするのに反して、独りぼっちであること(ロンリネス)は他の人々と一緒にいるときに最もはっきりとあらわれてくる。これについてはいくつかの感想が散見するが――それらはたいてい《nunquan minus solum esse quam solus esset》すなわち「彼は一人でいたときほど孤独ではなかった」、もっと精確には「彼は孤独でいたときほど独りぼっち(ロンリー)でなかったことはなかった」というカトーの言葉のように逆説的な言い方で言われているのだが――、それらを別にすれば、独りぼっちであること(ロンリネス)と孤独との区別を最初に行ったのはギリシャ生まれの解放奴隷で哲学者だったエピクテトスであったらしい。彼が主として興味を抱いたのは孤独でも独りぼっちであること(ロンリネス)でもなく、絶対的自立という意味で<独り>(monos)であるということだったのだから、ある意味では彼の発見は偶然だった。エピクテトスの見ているように、独りぼっち(ロンリー)の人間(eremos)は他人に囲まれながら、彼らと接触することができず、あるいはまた彼らの敵意にさらされている。これに反して孤独な人間は独りきりであり、それゆえ「自分自身と一緒にいることができる」。人間は「自分自身と話す」能力を持っているからである。換言すれば、孤独において私は「私自身のもとに」、私の自己と一緒におり、だから<一者のうちにある二者>であるが、それに反して独りぼっちであること(ロンリネス)の中では私は実際に一者であり、他のすべてのものから見捨てられているのだ。厳密に言えばすべての思考は孤独のうちになされ、私と私自身との対話である。しかしこの<一者のうちにある二者>の対話は、私の同胞たちの世界との接触を失うことはない。なぜなら彼らは、私がそれを相手に思考の対話を行う私の自己に代表されているからである。孤独が担っている問題となるためには他者を必要とすることだ。私が自分のアイデンティティを確証しようとすれば、全面的に彼らの分裂を解消させ、彼らを思考の対話――この対話の中では人間はあくまで曖昧な存在たるにとどまる――から救い出し、アイデンティティを回復させるからである。このアイデンティティのおかげで、彼らは交換不可能な人格の単一の声で語ることができるのだ。孤独が独りぼっちであること(ロンリネス)になることもある。そうなるのは、私が完全に自分だけを頼りにするようになって、その結果、自分の自己から打ち捨てられているときである。孤独な人々には、彼らを二重性と曖昧性と疑惑から救ってくれる交際という救済をもはや見出し得ないときにはいつも独りぼっちであること(ロンリネス)におちいる危険があった。歴史的に言えば、この危険が増大して人々に注目され、歴史に記録されることになったのは、ようやく19世紀になってからのようだ。孤独というものを一つの生き方とし、仕事をするための条件としているのは哲学者だけだが、その哲学者たちがもはや「哲学は少数者のためにのみ存在する」という事実に満足できなくなり、誰も自分たちを<理解>してくれないと主張しはじめたときに、この危険ははっきりとあらわれてきた。この間の事情をよく物語っているのはヘーゲルの臨終の際のある逸話であるが、彼以前のいかなる大哲学者についてもこういう逸話が語られることはまずないだろう。「ただ一人を除いて私を理解してくれたものはなかった。そしてその一人も私を誤解していた」と彼は言ったというのだ。一方また、独りぼっち(ロンリー)の人間が自分自身を発見し、孤独の対話的思考を始める可能性もつねにある。シルス・マリーアで『ツアラトゥストラ』を発想したときのニーチェにもそういうことがあったらしい。二編の詩(《Sils Maria》と《Aus hohen Bergen》)の中で彼は、独りぼっち(ロンリー)の人間の虚しい期待と憧れつつ待つことを語っている。やがて突然、《Um Mittag war’s, da wurde Eins zu Zwei…/Nun feiern wir,verein》(「時は真昼、そのとき一は二となった……今や祝おう、力を合わせた勝利を信じて、祝祭の中の祝祭を。客の中の客たる、友ツアラトゥストラがやって来たのだ!」
独りぼっちであること(ロンリネス)をこれほど耐えがたいものにするのは自己喪失ということである。自己は孤独の中で現実化され得るが、そのアイデンティティを確認してくれるのは、われわれの信頼してくれ、そしてこちらからも信頼することができる同輩たちの存在だけなのだ。独りぼっち(ロンリー)の状況においては、人間は自分の思考の相手である自分自身への信頼と、世界へのあの根本的な信頼を失うことになる。人間が経験するために必要なのはこの信頼なのだ。自己と世界が、思考と経験を行う能力が、ここでは一挙に失われてしまうのである。
人間の精神の能力で、確実に機能するために自己も他者も世界も必要とせず、経験にも思考にも依存していない唯一のものは、自明性をもってその前提とする論理的推論の能力である。否応のない自明性の基本的原則、2+2=4という自明の理(トゥルーイズム)は、絶対的な独りぼっちであること(ロンリネス)のもとにおいてすらも枉げられることはあり得ない。これは、人間が経験するため、生活するため、そして共通の世界の中で彼らの進むべき道を知るために必要とする相互的な保障を失ったとき、すなわちコモン・センスを失ったときにもなお頼ることのできる、唯一の信頼できる<真理>である。だがこの真理は空虚である。いや、むしろこれは全然真理などというものではないのだ。なぜならそれは何ものをも啓示しないのだから。(幾人かの現代の論理学者のように無矛盾性を真理と定義することは、真理の存在を否定することを意味する)それゆえ独りぼっちであること(ロンリネス)の条件のもとでは、自明性というものはもはや単なる悟性の手段ではなくなり、生産的になりはじめ、それ自身の<思考>の経路を展開させはじめる。どう見ても何らの逃げ道もない厳密な自明的論理性によって特徴づけられる思考過程が独りぼっちであること(ロンリネス)と何らかの関係をもつことは、「人間が孤独であることはよくない」という聖書の言葉についてのあまり知られていない註解の中で、ルターがつとに指摘していることである。(孤独と独りぼっちであること(ロンリネス)について彼自身が嘗めた経験はおそらく何ぴとにも劣らぬものだったろうし、彼は一度「人間には彼が信頼することのできる存在が必要だから、神が存在しなければならない」とまで言った)独りぼっちの(ロンリー)人間は「いつも次から次へと演繹を行い、すべてを最も悪く考える」とルターは言っている。全体主義運動の有名な極端主義(エクストレミズム)は、真のラディカリズムと何らかの関係があるどころか、実はこの「すべてを最も悪く考えること」、つねに最悪の結論に達するこの演繹の過程にほかならないのである。
非全体主義の世界の中で人びとに全体主義支配を受け容れさせてしまうものは、普通はたとえば老齢というようなある例外的な社会条件の中で人びとの嘗める限界的経験だった独りぼっちであること(ロンリネス)が、現代の絶えず増大する大衆の日常的経験となってしまったという事実である。全体主義が大衆をその中で組織した無慈悲な過程は、この現実からの自殺的な脱走のように見える。「君を万力のようにしめつける」「水のように冷たい推論」も、弁証法の「力強い触手」も、何ぴとも何ものも信頼できない世界の中での最後の支点のように見えてくる。それは内的な強制であり、その唯一の内容は一切の矛盾を避けるということでしかない。そしてこの矛盾の回避が、他者との一切の関係の外で人間のアイデンティティを確証するように見えるのである。それは人間が一人でいる場合にすらもその人間をテロルの鉄の箍に嵌めこむ。しかも全体主義支配は、独房に監禁するという極端な場合を除いて決して人間を一人にしておこうとはしない。人間と人間のあいだの一切の空間をなくし、人間と人間とを押しつけることで、孤立のもつ生産的な可能性すらも無に帰せられてしまう。独りぼっちであること(ロンリネス)の中では、すべての過程の出発点にあった最初の前提を取り逃がしてしまったら完全に破滅してしまうことがわかっているのだが、そのような独りぼっちであること(ロンリネス)の論理の働きを教え、それを賛美することによって、独りぼっちであること(ロンリネス)が孤独に変わり、論理が思想に変わるほんのわずかの可能性も消し去られてしまう。このやり方を暴政のやり方と比較すると、沙漠そのものを動かし、無人の地球のありとあらゆる部分を蔽いかねない砂嵐を巻き起こす方法がこれで見つかったというように見える。
《Initium ut esset homo est》――「始まりが為されんために人間は創られた」とアウグスティヌスは言った。この始まりは一人一人の人間の誕生ということによって保障されている。始まりとは、実は一人一人の人間なのだ。
そして「英語版第13章 イデオロギーとテロル――新しい形式」というエピローグを書いています。これも引用抜粋します。
[…]人間と法との同一化は、古代以来の法思想の悩みの種だった合法性と正義との差を解消するもののように見えるが、これはlumen naturale(自然の光)もしくは良心の声とは何ひとつ共通するものを持たない。ius naturale(自然法)もしくは歴史を通じて啓示された神の掟の権威の源泉としての<自然>もしくは<神>は、自然の光(ルーメン・ナチュラーレ)もしくは良心の声を通じて、その権威を人間自身の内面に告知すると考えられているのだが、しかしこのことは決して人間を法の生きた具現にはせず、反対に法は、人間に同意と服従を要求する権威として人間とは異なるものとされていたのである。実定法の権威の源泉としての<自然>もしくは<神>は永遠不易なものと考えられていた。実定法はその時その時の事情によって変化しつつあるもの、可変的なものだったが、しかしもっと急速に変わる人間の営為にくらべれば相対的な不変性を持っていた。そしてこの不変性は、その権威の源泉が永遠に存在することから来ていた。だから実定法は本来、絶えず変わる人間の動きを安定化する要因として機能するよう考えられていたのだ。
全体主義の解釈によれば、すべての法は運動の法則になっている。ナチが自然の法則を、あるいはボリシェヴィキが歴史の法則を語るときには、自然も歴史も人間の行為にとっての安定的な権威の源泉ではもはやない。それらは運動そのものなのだ。自然法則の人間における表現としての人種法則としてのナチの信念の基底には、現生の人間という種ではかならずしも停止しない自然の発展の産物としての人間というダーウィンの観念がひそんでいるが、それとまったく同じく、歴史法則の表現としての階級闘争についてのボリシェヴィキの信念の基底には、それ自身の運動法則に従って消滅する歴史的時代の終末――そこでは歴史の動きそのものが消滅する――に向かって突っ走る巨大な歴史の動きの所産としての社会というマルクスの観念があるのだ。[…]
どちらもかなり抽象的であり、別なことを述べているようでいて、実は同じ文章が出てきます。共通した何かがあると感じました。わたしがアーレントを解説したり要約したりすることはできませんので、あとは各自でお読みになり解釈してください。
それから「独りぼっちでいること(ロンリネス)」について。わたしは独りでいることはまったく平気ですが、自分が「孤立」しているのかどうかはわかりません。確かに、わたしは集団のなかで「独りぼっちでいること」には耐えられそうにありませんし、早く集団のなかから抜けだして「独りぼっちでいること(自分自身であること)」を望みます。そのほうが安心なのです。だからといって、「根を絶たれた余計者的な人間の境遇」「他の人々によって承認され保障された席をこの世界に持っていない」「全然この世界に属していない」という感じがしません。つまり、「独りぼっちでいること」と「孤独、孤立(根を絶たれた余計者)」とは違うのです。
おそらくこれは、コロンバイン高校銃乱射事件や秋葉原通り魔事件と関係があるような気がします。
わたしは組織的集団で仕事をしたことはありません。これは、集団でなければできないことやチームワークの強さを否定するものではありませんが、一方で、集団は個々のメンバーを信頼し合うことが前提条件であり、メンバーを信頼して仕事の悩みを相談したり、「絆」を感じたりすることが、「スムースに仕事ができる」という理想にすぎないことを気づく者は少ないと思います。理想はつねに現実を裏切ります。わたしはこれ(集団行動)が苦手で、しばし独善的だと自分でも思いますが、誰かに相談するくらいなら自分一人で試行錯誤したほうがよほどましです。
これは想像ですが、会社でも家族でも、誰にも悩みを相談できずにいることが「孤独」かつ「不安」で、「自己喪失」の状態かもしれません。
ハンナ・アーレントの思考は、わたしには完全に理解することはできません。共通している感覚があっても勘違いかもしれません。しかし互いに「孤立」していることがナチス集団の残酷な行動の原因であり、その背景を想像するに、「思考停止」「長いものには巻かれろ」などがあったら、それは日本の官僚と同様です。2020年、国内のコロナによる死亡者数は「運命的に」少なかったのですが、そのような「カミカゼ」はもう吹きません。あとは自分たちが考えて政策を出すしかないのです。
(2021年8月21日)